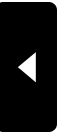2012年11月29日
介護ロボット開発の重点分野を発表
『介護ロボット開発の重点分野を発表- 厚労省と経産省』
(キャリアブレイン 2012年11月22日 20:30 )
厚生労働省と経済産業省は22日、介護ロボットの開発における重点分野を決定した。対象には、高齢者の外出をサポートするための歩行支援機器や、移乗を支援するための装着型機器など、4分野5項目が選ばれた。
今後、経産省と新エネルギー・産業技術総合開発機構は、重点分野の介護ロボット開発に積極的な企業を募集。応募した企業や厚労省、経産省などで協議体を組織し、実用化を目指す上での課題や、介護現場におけるニーズの洗い出しなどを行う。
重点分野に選ばれた項目は次の通り。
▽介助者のパワーアシストを行う装着型の機器
▽介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器
▽高齢者などの外出をサポートし、荷物などを安全に運搬できる歩行支援機器
▽排泄物の処理にロボット技術を活用しており、設置位置の調整可能なトイレ
▽介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えた機器のプラットフォーム
【ただ正芳】

(キャリアブレイン 2012年11月22日 20:30 )
厚生労働省と経済産業省は22日、介護ロボットの開発における重点分野を決定した。対象には、高齢者の外出をサポートするための歩行支援機器や、移乗を支援するための装着型機器など、4分野5項目が選ばれた。
今後、経産省と新エネルギー・産業技術総合開発機構は、重点分野の介護ロボット開発に積極的な企業を募集。応募した企業や厚労省、経産省などで協議体を組織し、実用化を目指す上での課題や、介護現場におけるニーズの洗い出しなどを行う。
重点分野に選ばれた項目は次の通り。
▽介助者のパワーアシストを行う装着型の機器
▽介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器
▽高齢者などの外出をサポートし、荷物などを安全に運搬できる歩行支援機器
▽排泄物の処理にロボット技術を活用しており、設置位置の調整可能なトイレ
▽介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えた機器のプラットフォーム
【ただ正芳】

2012年11月28日
在宅の情報、皆で共有は正しいのか・・・
こんにちは!ふくえん熊本の益田です(^^)/
「情報の共有」は大切だと考えますが、
広げすぎる(過度な)情報共有にはデメリットも考えられるのですね、、、
しかし、「情報の最適化」=適切な情報・価値ある情報の判断と選択って難しいような気もします
『在宅の情報、皆で共有は正しいのか- 家族「不要な情報排除してこそ決断できる」』
(キャリアブレイン 2012年11月20日 16:11)
第32回医療情報学連合大会がこのほど、新潟市で開かれ、「在宅医療における医療介護福祉連携」と題したシンポジウムが行われた。チーム医療では情報共有が欠かせないといわれる中、在宅医療における患者や家族の意思決定を考えた場合、すべての職種が同じ情報を共有することが、必ずしも良い結果をもたらさないことも指摘された。

「在宅医療における医療介護福祉連携」と題したシンポジウムでは、関係者全員で均等な情報共有をすることのデメリットも指摘された
祖母を在宅で15年間介護した宮崎詩子氏(介護相談サロン「ソワニエグラン」代表)は、在宅で看取る上で、家族がどのような情報を望んでいるのかを体験を基に報告した。
宮崎氏は、終末期ケアは家族の領域と考えており、医療や福祉、地域や行政などは、家族が終末期ケアをやり遂げるためのサポーターという共通認識をはぐくむことが、多職種連携の基盤になるのではないかと述べた。
また、家族は医師との人間関係を築き、病状変化の具体例や看取りの様子、段取りを教えてもらうことで、必要な情報は何なのかが見えてくるとした。そして、祖母の介護で情報が集まってきた時、連携の推進役となったのは、家族だったという。
祖母の看取りでは、胃ろうを含むすべての医療、ケアを終了させるという形を選んだ。祖母が絶食状態となってから、亡くなるまでの10日間は、別れを惜しむための豊かな時間になったが、一方で終末期の判断を適切に行うために、体調の変化に注目し、ケアの在り方を再検討することは、簡単ではなかったという。
その際、意識的に第三者が見ても納得できる情報を積み上げていった。栄養量については、家族、医師、看護師の3者間での情報共有のために、摂取カロリーの推移を表に記録していった。
宮崎氏は、栄養量の記録は終末期の判断について、根拠を残すことが目的であったため、終末期の代理判断にかかわらないケアマネジャーとは、情報を共有しなかったという。
その理由として、もし情報共有の範囲を広げた場合、親切心からさまざまな職種が意見を述べ、不用意な発言が家族の心理的な負担となってしまい、満足のいく決断が妨げられることも考えられたためだとした。
宮崎氏は、臨死期への移行を決めるには、適切な情報が必要と言い、終末期を示す情報があったとしても、埋もれていては価値がないと指摘。多職種間の情報共有において、情報は連携のツールではなく、判断材料である点を忘れてほしくないとした。
宮崎氏は、家族が欲しい情報について「突き詰めれば、心残りの解決と安らかな旅立ちの実現に役立つ情報だけかもしれない」と指摘。また、安らかな死を迎えさせるために、患者本人が発するサインを感じ取れるかどうかが、代理判断者としての家族に求められる責任だと考えれば、「不要な情報を排除してこそ、選択し、決断することができる」と述べた。さらに、家族が代理判断を行う上で、医療情報が重要なツールとなり、在宅医療で豊かな看取りの文化がはぐくまれることを願っているとした。
■均等な共有は、患者・家族を悩ませることも
病院と在宅医療・介護関係者の調整役である「在宅医療コーディネーター」を務める訪問看護師の水木麻衣子氏(東大大学院医学系研究科)は、在宅医療における情報の最適化の在り方について報告した。
東京都豊島区で設けられている在宅医療コーディネーターは、在宅ケアにおいて患者・家族の意思決定を支援し、関係者の合意形成を担っていく役割があるという。
水木氏は、患者・家族を支えるために必要な情報は、職種によって異なり、在宅医療コーディネーターは、各職種が行動できるよう適切に伝える必要があると指摘。その一方で、各職種に均等に情報を伝えることで、不具合が起こることがあると強調した。
例えば、がん末期の患者が在宅で療養する場合、家族は家で支えられるか不安に思ったり、患者も家族の負担にならないか悩んだりする。
それに対し、在宅医、訪問看護師、薬剤師が意思決定に協力しようと、各自の判断でアドバイスすることで、むしろ患者・家族の意思決定が揺らいでしまうことがあるという。
水木氏は、さまざまな情報を与えられ、意思決定に迷ってしまう患者・家族を支えるため、在宅医療コーディネーターは情報をコントロールする役割もあるとした。
また、高齢者の在宅ケアは、ターミナルの状態だと考えられても、長期化する傾向もあるため、水木氏は、半年に1回などとタイミングを決めて、患者の状態の変化と方針を話し合ってはどうかと提案した。
水木氏は、適切な内容を適切な時期に提供することで、患者・家族の意思決定を安定させられるとした。そして、情報を均等に共有させるのではなく、患者・家族にとって価値のある情報を、身体状況に変化が生じた時などのタイミングで、共有すべき人と共有し、情報の最適化を図るべきと訴えた。
セコム医療システム・薬剤サービス部の黒岩泰代氏は、在宅訪問服薬指導をする薬剤師の立場から報告した。
在宅では、患者宅に置かれた「介護ノート」が情報共有ツールになっていることが多いが、黒岩氏は、それぞれの職種がランダムに情報を記載していることも多いと指摘。また、大事な情報がどこにあるのか、いつの情報なのかといったことが、なかなか把握しづらいとした。
薬剤師が訪問服薬指導にかかわるのは週1回程度だが、その頻度では介護ノートを読み切ることが難しく、情報も古くなってしまうことがあるという。
訪問服薬指導を終えると、訪問報告書を作成しているが、以前は情報の羅列で終わることもあったという。アセスメントをしたが、処方せんに反映されなかった時、医師に理由を聞いたところ、情報を羅列しているだけでよく分からないと言われた。
現在では、カンファレンスの際、医師がどのような情報を必要としているのかを確認した上で報告書を作成し、医師に活用してもらおうと考えている。
このほか、訪問先で転倒してしまったという話を聞いても、薬剤師としてどう対応すればよいのか迷う場面もあることから、訪問服薬指導で得られた情報を、他の職種が必要とするレベルで伝えられるかが、今後の課題とした。【大戸豊】
「情報の共有」は大切だと考えますが、
広げすぎる(過度な)情報共有にはデメリットも考えられるのですね、、、

しかし、「情報の最適化」=適切な情報・価値ある情報の判断と選択って難しいような気もします

『在宅の情報、皆で共有は正しいのか- 家族「不要な情報排除してこそ決断できる」』
(キャリアブレイン 2012年11月20日 16:11)
第32回医療情報学連合大会がこのほど、新潟市で開かれ、「在宅医療における医療介護福祉連携」と題したシンポジウムが行われた。チーム医療では情報共有が欠かせないといわれる中、在宅医療における患者や家族の意思決定を考えた場合、すべての職種が同じ情報を共有することが、必ずしも良い結果をもたらさないことも指摘された。

「在宅医療における医療介護福祉連携」と題したシンポジウムでは、関係者全員で均等な情報共有をすることのデメリットも指摘された
祖母を在宅で15年間介護した宮崎詩子氏(介護相談サロン「ソワニエグラン」代表)は、在宅で看取る上で、家族がどのような情報を望んでいるのかを体験を基に報告した。
宮崎氏は、終末期ケアは家族の領域と考えており、医療や福祉、地域や行政などは、家族が終末期ケアをやり遂げるためのサポーターという共通認識をはぐくむことが、多職種連携の基盤になるのではないかと述べた。
また、家族は医師との人間関係を築き、病状変化の具体例や看取りの様子、段取りを教えてもらうことで、必要な情報は何なのかが見えてくるとした。そして、祖母の介護で情報が集まってきた時、連携の推進役となったのは、家族だったという。
祖母の看取りでは、胃ろうを含むすべての医療、ケアを終了させるという形を選んだ。祖母が絶食状態となってから、亡くなるまでの10日間は、別れを惜しむための豊かな時間になったが、一方で終末期の判断を適切に行うために、体調の変化に注目し、ケアの在り方を再検討することは、簡単ではなかったという。
その際、意識的に第三者が見ても納得できる情報を積み上げていった。栄養量については、家族、医師、看護師の3者間での情報共有のために、摂取カロリーの推移を表に記録していった。
宮崎氏は、栄養量の記録は終末期の判断について、根拠を残すことが目的であったため、終末期の代理判断にかかわらないケアマネジャーとは、情報を共有しなかったという。
その理由として、もし情報共有の範囲を広げた場合、親切心からさまざまな職種が意見を述べ、不用意な発言が家族の心理的な負担となってしまい、満足のいく決断が妨げられることも考えられたためだとした。
宮崎氏は、臨死期への移行を決めるには、適切な情報が必要と言い、終末期を示す情報があったとしても、埋もれていては価値がないと指摘。多職種間の情報共有において、情報は連携のツールではなく、判断材料である点を忘れてほしくないとした。
宮崎氏は、家族が欲しい情報について「突き詰めれば、心残りの解決と安らかな旅立ちの実現に役立つ情報だけかもしれない」と指摘。また、安らかな死を迎えさせるために、患者本人が発するサインを感じ取れるかどうかが、代理判断者としての家族に求められる責任だと考えれば、「不要な情報を排除してこそ、選択し、決断することができる」と述べた。さらに、家族が代理判断を行う上で、医療情報が重要なツールとなり、在宅医療で豊かな看取りの文化がはぐくまれることを願っているとした。
■均等な共有は、患者・家族を悩ませることも
病院と在宅医療・介護関係者の調整役である「在宅医療コーディネーター」を務める訪問看護師の水木麻衣子氏(東大大学院医学系研究科)は、在宅医療における情報の最適化の在り方について報告した。
東京都豊島区で設けられている在宅医療コーディネーターは、在宅ケアにおいて患者・家族の意思決定を支援し、関係者の合意形成を担っていく役割があるという。
水木氏は、患者・家族を支えるために必要な情報は、職種によって異なり、在宅医療コーディネーターは、各職種が行動できるよう適切に伝える必要があると指摘。その一方で、各職種に均等に情報を伝えることで、不具合が起こることがあると強調した。
例えば、がん末期の患者が在宅で療養する場合、家族は家で支えられるか不安に思ったり、患者も家族の負担にならないか悩んだりする。
それに対し、在宅医、訪問看護師、薬剤師が意思決定に協力しようと、各自の判断でアドバイスすることで、むしろ患者・家族の意思決定が揺らいでしまうことがあるという。
水木氏は、さまざまな情報を与えられ、意思決定に迷ってしまう患者・家族を支えるため、在宅医療コーディネーターは情報をコントロールする役割もあるとした。
また、高齢者の在宅ケアは、ターミナルの状態だと考えられても、長期化する傾向もあるため、水木氏は、半年に1回などとタイミングを決めて、患者の状態の変化と方針を話し合ってはどうかと提案した。
水木氏は、適切な内容を適切な時期に提供することで、患者・家族の意思決定を安定させられるとした。そして、情報を均等に共有させるのではなく、患者・家族にとって価値のある情報を、身体状況に変化が生じた時などのタイミングで、共有すべき人と共有し、情報の最適化を図るべきと訴えた。
セコム医療システム・薬剤サービス部の黒岩泰代氏は、在宅訪問服薬指導をする薬剤師の立場から報告した。
在宅では、患者宅に置かれた「介護ノート」が情報共有ツールになっていることが多いが、黒岩氏は、それぞれの職種がランダムに情報を記載していることも多いと指摘。また、大事な情報がどこにあるのか、いつの情報なのかといったことが、なかなか把握しづらいとした。
薬剤師が訪問服薬指導にかかわるのは週1回程度だが、その頻度では介護ノートを読み切ることが難しく、情報も古くなってしまうことがあるという。
訪問服薬指導を終えると、訪問報告書を作成しているが、以前は情報の羅列で終わることもあったという。アセスメントをしたが、処方せんに反映されなかった時、医師に理由を聞いたところ、情報を羅列しているだけでよく分からないと言われた。
現在では、カンファレンスの際、医師がどのような情報を必要としているのかを確認した上で報告書を作成し、医師に活用してもらおうと考えている。
このほか、訪問先で転倒してしまったという話を聞いても、薬剤師としてどう対応すればよいのか迷う場面もあることから、訪問服薬指導で得られた情報を、他の職種が必要とするレベルで伝えられるかが、今後の課題とした。【大戸豊】
2012年11月27日
在宅介護者の56%が「介護用ベッドの注意喚起を・・・
こんにちは!ふくえん熊本の益田です
何よりもまずは「安全第一」ですね(^_^) でかっ、、、
『在宅介護者の56%が「介護用ベッドの注意喚起を知らない」――消費者庁・調査結果』
(ケアマネジメントオンライン 2012/11/15 09:00 配信)
消費者庁は、介護ベッドについての注意喚起が介護者にどの程度伝わっているかを把握するための調査を行い、このほどその結果を発表した。
医療・介護ベッドの事故の危険性については、事業者や行政(消費者庁、厚生労働省、経済産業省)がたびたび注意喚起を行ってきたが、依然として死亡事故や重大事故が続き、今年度もすでに4件の死亡事故が発生している。その現状を踏まえ、全国の在宅介護者向けにアンケート調査を行った。
その結果、これまでの注意喚起が在宅介護者の半数以上に伝わっておらず、伝わっていたとしても危険性を感じず、対策を講じていない介護者が多いことが分かった。消費者庁ではこの調査結果を深刻に受け止め、厚生労働省、経済産業省と協議し、連携して在宅介護者に確実に事故の危険性を伝えるための取り組みを実施する。
【事故の危険性を伝えるための取り組み】
■福祉用具貸与事業者への緊急依頼
貸与時もしくはモニタリング時に、介護ベッドにかかわる事故の危険性と対応策が介護者に確実に伝わるよう、説明することを依頼する。
■全国の各地方自治体への協力依頼
市報、区報などに介護ベッドにかかわる事故の危険性などがわかるマークの掲載を依頼する。
■テレビ・新聞を通じた広報
政府広報などを有効に使い、広報効果の大きいテレビや新聞を通じて注意喚起を行う。
【調査の概要】
■調査の対象:
在宅での介護に携わっている9,573 人のうち、介護ベッドを使っている(いた)人
出現率:37.4%、総サンプル数:3,578 人
回収地域:47 都道府県
平均年齢:49.8 歳
男女比 男:36.5%、女:63.5%
■調査方法:Web によるアンケート調査
■調査の時期:2012 年10 月
調査の主な結果は以下の通り。
■介護ベッドの事故は知っていても、注意喚起は知らない人も
「医療・介護ベッドによる事故が発生し、問題になっていることを知っているか」という質問には、「はい」は57.9%、「いいえ」は42.1%。「医療・介護ベッドの危険性について、行政やベッドメーカーから注意喚起が行われていることを知っているか」では、「はい」43.7%、「いいえ」56.3%だった。注意喚起を知っていると答えた人に、「どのように知ったか」を訊ねたところ(複数回答)、新聞47.5%、テレビ54.6%、ラジオ3.5%、チラシ8.3%、インターネット:19.1%、携帯サイト1.2%、雑誌4.8%、メール2.0%、事業者(ベッドメーカー、レンタル会社または販売会社)からの説明またはマニュアルが42.2%、その他5.4%だった。
■注意喚起を知っていても、4割強が「特に対応していない」
注意喚起を知っていると答えた人に、「事故が起こらないようにどのような対応をとっているか」を訊ねたところ(複数回答)、「ベッド自体を新しいものに取り換えた」8.5%、「ベッド手すりに安全補助具を取り付けた」32.6%、「すき間にクッションや毛布を詰めた」31.2%、「その他」4.4%、「特に対応していない」42.4%だった。
「特に対応していない」と答えた人に、「どのような理由から対応をしていないのか」を訊ねたところ(複数回答)、「特に事故の危険性を感じない」71.0%、「安全補助具が必要と感じるが入手できていない」8.7%、「安全補助具などの対策を被介護者が拒否する」4.7%、「安全補助具などの取り付けは介護に支障がある(遠くから被介護者の様子が見えないなど)」6.8%、「その他」16.0%だった。
■介護ベッドの危険を感じたことがあるのは3割近く
「今まで医療・介護ベッドを使用していて、被介護者への危険を感じたことはあるか」という質問では、「はい」が28.4%、「いいえ」が71.6%だった。「はい」と答えた人に、「危険を感じたのは、どのような状況だったか」を訊ねたところ(複数回答)、「すき間(ボードとサイドレールの間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」36.5%、「すき間(ボードとサイドレールの間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」34.6%、「すき間(サイドレール自体の空間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」17.7%、「ベッドから落ちた(ずり落ちた)」49.5%、「その他」12.1%だった。
また、同時期に、全国の病院や介護施設などで介護に従事している(いた)人を対象に、注意喚起に基づいて安全を意識した対応を行っているかを調査したところ、3,165 人のうち1,676人 の回答があった。回答者に「医療・介護ベッドによる事故が発生し、問題になっていることを知っているか」を訊ねたところ、「はい」が72.6%、「いいえ」が27.4%。また、「医療・介護ベッドの危険性について、行政やベッドメーカーから注意喚起が行われていることを知っているか」では、「はい」が60.6%、「いいえ」が39.4%だった。
◎消費者庁

何よりもまずは「安全第一」ですね(^_^) でかっ、、、
『在宅介護者の56%が「介護用ベッドの注意喚起を知らない」――消費者庁・調査結果』
(ケアマネジメントオンライン 2012/11/15 09:00 配信)
消費者庁は、介護ベッドについての注意喚起が介護者にどの程度伝わっているかを把握するための調査を行い、このほどその結果を発表した。
医療・介護ベッドの事故の危険性については、事業者や行政(消費者庁、厚生労働省、経済産業省)がたびたび注意喚起を行ってきたが、依然として死亡事故や重大事故が続き、今年度もすでに4件の死亡事故が発生している。その現状を踏まえ、全国の在宅介護者向けにアンケート調査を行った。
その結果、これまでの注意喚起が在宅介護者の半数以上に伝わっておらず、伝わっていたとしても危険性を感じず、対策を講じていない介護者が多いことが分かった。消費者庁ではこの調査結果を深刻に受け止め、厚生労働省、経済産業省と協議し、連携して在宅介護者に確実に事故の危険性を伝えるための取り組みを実施する。
【事故の危険性を伝えるための取り組み】
■福祉用具貸与事業者への緊急依頼
貸与時もしくはモニタリング時に、介護ベッドにかかわる事故の危険性と対応策が介護者に確実に伝わるよう、説明することを依頼する。
■全国の各地方自治体への協力依頼
市報、区報などに介護ベッドにかかわる事故の危険性などがわかるマークの掲載を依頼する。
■テレビ・新聞を通じた広報
政府広報などを有効に使い、広報効果の大きいテレビや新聞を通じて注意喚起を行う。
【調査の概要】
■調査の対象:
在宅での介護に携わっている9,573 人のうち、介護ベッドを使っている(いた)人
出現率:37.4%、総サンプル数:3,578 人
回収地域:47 都道府県
平均年齢:49.8 歳
男女比 男:36.5%、女:63.5%
■調査方法:Web によるアンケート調査
■調査の時期:2012 年10 月
調査の主な結果は以下の通り。
■介護ベッドの事故は知っていても、注意喚起は知らない人も
「医療・介護ベッドによる事故が発生し、問題になっていることを知っているか」という質問には、「はい」は57.9%、「いいえ」は42.1%。「医療・介護ベッドの危険性について、行政やベッドメーカーから注意喚起が行われていることを知っているか」では、「はい」43.7%、「いいえ」56.3%だった。注意喚起を知っていると答えた人に、「どのように知ったか」を訊ねたところ(複数回答)、新聞47.5%、テレビ54.6%、ラジオ3.5%、チラシ8.3%、インターネット:19.1%、携帯サイト1.2%、雑誌4.8%、メール2.0%、事業者(ベッドメーカー、レンタル会社または販売会社)からの説明またはマニュアルが42.2%、その他5.4%だった。
■注意喚起を知っていても、4割強が「特に対応していない」
注意喚起を知っていると答えた人に、「事故が起こらないようにどのような対応をとっているか」を訊ねたところ(複数回答)、「ベッド自体を新しいものに取り換えた」8.5%、「ベッド手すりに安全補助具を取り付けた」32.6%、「すき間にクッションや毛布を詰めた」31.2%、「その他」4.4%、「特に対応していない」42.4%だった。
「特に対応していない」と答えた人に、「どのような理由から対応をしていないのか」を訊ねたところ(複数回答)、「特に事故の危険性を感じない」71.0%、「安全補助具が必要と感じるが入手できていない」8.7%、「安全補助具などの対策を被介護者が拒否する」4.7%、「安全補助具などの取り付けは介護に支障がある(遠くから被介護者の様子が見えないなど)」6.8%、「その他」16.0%だった。
■介護ベッドの危険を感じたことがあるのは3割近く
「今まで医療・介護ベッドを使用していて、被介護者への危険を感じたことはあるか」という質問では、「はい」が28.4%、「いいえ」が71.6%だった。「はい」と答えた人に、「危険を感じたのは、どのような状況だったか」を訊ねたところ(複数回答)、「すき間(ボードとサイドレールの間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」36.5%、「すき間(ボードとサイドレールの間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」34.6%、「すき間(サイドレール自体の空間)に首や腕など身体の一部を挟んだ」17.7%、「ベッドから落ちた(ずり落ちた)」49.5%、「その他」12.1%だった。
また、同時期に、全国の病院や介護施設などで介護に従事している(いた)人を対象に、注意喚起に基づいて安全を意識した対応を行っているかを調査したところ、3,165 人のうち1,676人 の回答があった。回答者に「医療・介護ベッドによる事故が発生し、問題になっていることを知っているか」を訊ねたところ、「はい」が72.6%、「いいえ」が27.4%。また、「医療・介護ベッドの危険性について、行政やベッドメーカーから注意喚起が行われていることを知っているか」では、「はい」が60.6%、「いいえ」が39.4%だった。
◎消費者庁
2012年11月26日
三好春樹氏、認知症ケアの最深部を鋭くえぐる・・・
おはようございます。ふくえん熊本の益田です
毒舌家で「介護界のきみまろ」とも言われる三好春樹先生の講演、、、要チェックです
三好春樹氏、認知症ケアの最深部を鋭くえぐる——「認知症ケアの最前線」レポ(1)
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/06 09:00 配信)
8月18日、東京都内で雲母書房の主催の「認知症ケアの最前線-三好春樹+宅老所よりあい講演会」が行われた。
講師は、「生活とリハビリ研究所」主宰の三好春樹氏、福岡県の「宅老所よりあい」の村瀨孝生氏と下村恵美子氏。高齢者のケアに長く携わり、一貫して介護の現場に足を置いた発言を行っている3氏が一堂に会する貴重な機会とあって、会場は多くの聴衆で埋まった。
トップバッターを務めた三好春樹氏は、理学療法士。介護技術や高齢者の生活づくりの指導を行うほか、豊富な現場経験をベースに高齢者ケアや介護という仕事についての思索を深め、『痴呆論』などの著者や講演でさまざまな提言を行っている。
講演は、認知症ケアの通念を問い直しながら、東日本大震災を経た日本のこれからと介護の可能性にも及ぶ視野の広いものとなった。
三好氏は、まず「今日のテーマは『認知症ケアの最前線』ですが、私の話は『最深部』になると思います」と前置きした上で、認知症を脳の病気と見る医学的なアプローチでは、認知症高齢者ケアにとって大切な「ひとりの人間として理解する」という視点が抜け落ちてしまうと批判した。

認知症に伴う周辺症状=BPSDについても、いわゆる「問題行動」を起こすのは、すべてが認知症のせいなのか?と疑問を述べ、「夜勤を誰がするかによって問題が起きる場合がありますよね(会場・爆笑)、それなら相性の問題ということになります。症状を抑えようと安易に薬を投与し、夜眠らないなどの問題を起こしている場合もあります」。
問題行動とは、「その人が何か訴えたいことの非言語的表現ではないか」というのが三好氏の考え方で、問題行動を「あるべきでないこと」として、薬で抑え込む「治療」では人と人とのコミュニケーション=ケアが成り立たない、「医療のように一元的ではなく、豊かな方法論があるのが介護という仕事です」と語った。
さらに、「介護の豊かな方法論は、東日本大震災後を生きる私たちにもうひとつの価値観を示すことができるはずです。それは、原発に代表される経済至上主義に替わるものであり、協調される『絆』からこぼれ落ちる人たちと連帯する可能性も秘めています」と語り、文化人類学的視点も援用しながら今の日本社会と介護のこれからを俯瞰する論へと発展した。
38年前、特別養護老人ホームに勤務した時以来出会ったたくさんの高齢者や介護スタッフのエピソードを盛り込みながら、時にユーモラスに、時に熱く語った三好氏。聴衆の気をそらさない語りのテクニックも見事。会場からはたびたび笑い声が起こり、介護の現場で感じ、考えたこと——怒りを覚えたこと、無力感に襲われたこと、それを超える感動と希望を介護の仕事に取り組む人たちが共有していることが伝わる講演となった。
生活とリハビリ研究所

12月15日(土)10:00~16:45 熊本学園大学

毒舌家で「介護界のきみまろ」とも言われる三好春樹先生の講演、、、要チェックです

三好春樹氏、認知症ケアの最深部を鋭くえぐる——「認知症ケアの最前線」レポ(1)
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/06 09:00 配信)
8月18日、東京都内で雲母書房の主催の「認知症ケアの最前線-三好春樹+宅老所よりあい講演会」が行われた。
講師は、「生活とリハビリ研究所」主宰の三好春樹氏、福岡県の「宅老所よりあい」の村瀨孝生氏と下村恵美子氏。高齢者のケアに長く携わり、一貫して介護の現場に足を置いた発言を行っている3氏が一堂に会する貴重な機会とあって、会場は多くの聴衆で埋まった。
トップバッターを務めた三好春樹氏は、理学療法士。介護技術や高齢者の生活づくりの指導を行うほか、豊富な現場経験をベースに高齢者ケアや介護という仕事についての思索を深め、『痴呆論』などの著者や講演でさまざまな提言を行っている。
講演は、認知症ケアの通念を問い直しながら、東日本大震災を経た日本のこれからと介護の可能性にも及ぶ視野の広いものとなった。
三好氏は、まず「今日のテーマは『認知症ケアの最前線』ですが、私の話は『最深部』になると思います」と前置きした上で、認知症を脳の病気と見る医学的なアプローチでは、認知症高齢者ケアにとって大切な「ひとりの人間として理解する」という視点が抜け落ちてしまうと批判した。

認知症に伴う周辺症状=BPSDについても、いわゆる「問題行動」を起こすのは、すべてが認知症のせいなのか?と疑問を述べ、「夜勤を誰がするかによって問題が起きる場合がありますよね(会場・爆笑)、それなら相性の問題ということになります。症状を抑えようと安易に薬を投与し、夜眠らないなどの問題を起こしている場合もあります」。
問題行動とは、「その人が何か訴えたいことの非言語的表現ではないか」というのが三好氏の考え方で、問題行動を「あるべきでないこと」として、薬で抑え込む「治療」では人と人とのコミュニケーション=ケアが成り立たない、「医療のように一元的ではなく、豊かな方法論があるのが介護という仕事です」と語った。
さらに、「介護の豊かな方法論は、東日本大震災後を生きる私たちにもうひとつの価値観を示すことができるはずです。それは、原発に代表される経済至上主義に替わるものであり、協調される『絆』からこぼれ落ちる人たちと連帯する可能性も秘めています」と語り、文化人類学的視点も援用しながら今の日本社会と介護のこれからを俯瞰する論へと発展した。
38年前、特別養護老人ホームに勤務した時以来出会ったたくさんの高齢者や介護スタッフのエピソードを盛り込みながら、時にユーモラスに、時に熱く語った三好氏。聴衆の気をそらさない語りのテクニックも見事。会場からはたびたび笑い声が起こり、介護の現場で感じ、考えたこと——怒りを覚えたこと、無力感に襲われたこと、それを超える感動と希望を介護の仕事に取り組む人たちが共有していることが伝わる講演となった。
生活とリハビリ研究所

12月15日(土)10:00~16:45 熊本学園大学
2012年11月17日
保険料納付者の8割余りが介護に・・・
『保険料納付者の8割余りが介護に「不安」 - オリックス・リビングが意識調査』
(キャリアブレイン 2012年11月13日 13:05 )
介護保険料を納める世代のうち、家族や自分の介護について不安を感じている人は8割余りに達することが、オリックス・リビングの調査で分かった。また、不安を感じる一方、将来の介護について、まだ何も考えていない人が7割近くいることも明らかになった。
オリックス・リビングでは、今年10月4日から5日にかけ、全国の40歳以上の男女1238人を対象に、介護に関する意識調査を実施した。
このうち、家族の介護に関する不安の有無について尋ねた質問では、不安(「不安を感じる」と「やや不安を感じる」の合計)と回答した人が全体の86.0%に達した。また、自分の介護についての不安の有無については、86.1%が不安と答えた。
一方、自分に介護が必要となった時について尋ねた質問では、68.4%が「まだ何も考えていない」と回答。「考えているが、家族には伝えていない」(23.9%)という回答と合わせると、「介護保険料を納める人のうち、92.3%が将来の介護に不安を抱えながらも、実質的には何の対応もしていないことになる」(オリックス・リビングの入江徹企画チーム長)。
■サ高住「詳しく理解している」が7.8%
このほか、昨年10月に導入されたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について、「詳しく理解している」人は7.8%にとどまった半面、「聞いたことはある」人は64.0%となった。また、自分が認知症になった場合、施設に入りたいと考える人は76.6%で、従来型の介護保険施設や有料老人ホームに期待する人が、多数派であることも浮き彫りとなった。
さらに、介護ロボットについて尋ねた質問では、ロボットからの介護を受けてもよいと考える人(「積極的に受けたい」「推奨されれば受けたい」の合計)は76.4%となり、「受けたくない」という答え(20.6%)を大きく上回った。【多●正芳、●は木へんに朶】

(キャリアブレイン 2012年11月13日 13:05 )
介護保険料を納める世代のうち、家族や自分の介護について不安を感じている人は8割余りに達することが、オリックス・リビングの調査で分かった。また、不安を感じる一方、将来の介護について、まだ何も考えていない人が7割近くいることも明らかになった。
オリックス・リビングでは、今年10月4日から5日にかけ、全国の40歳以上の男女1238人を対象に、介護に関する意識調査を実施した。
このうち、家族の介護に関する不安の有無について尋ねた質問では、不安(「不安を感じる」と「やや不安を感じる」の合計)と回答した人が全体の86.0%に達した。また、自分の介護についての不安の有無については、86.1%が不安と答えた。
一方、自分に介護が必要となった時について尋ねた質問では、68.4%が「まだ何も考えていない」と回答。「考えているが、家族には伝えていない」(23.9%)という回答と合わせると、「介護保険料を納める人のうち、92.3%が将来の介護に不安を抱えながらも、実質的には何の対応もしていないことになる」(オリックス・リビングの入江徹企画チーム長)。
■サ高住「詳しく理解している」が7.8%
このほか、昨年10月に導入されたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について、「詳しく理解している」人は7.8%にとどまった半面、「聞いたことはある」人は64.0%となった。また、自分が認知症になった場合、施設に入りたいと考える人は76.6%で、従来型の介護保険施設や有料老人ホームに期待する人が、多数派であることも浮き彫りとなった。
さらに、介護ロボットについて尋ねた質問では、ロボットからの介護を受けてもよいと考える人(「積極的に受けたい」「推奨されれば受けたい」の合計)は76.4%となり、「受けたくない」という答え(20.6%)を大きく上回った。【多●正芳、●は木へんに朶】

2012年11月16日
巨大商業施設「イオンモール」内に滞在型・・・
『巨大商業施設「イオンモール」内に滞在型・通所型デイサービスがオープン!』
(ケアマネジメントオンライン 2012/11/07 09:00 配信)
大型ショッピングモールを中心に、アミューズメント施設を全国に展開している株式会社UCOと全国にデイサービス「樹楽」、複合カフェ「コミックバスター」を展開している株式会社アクロスは、業務提携し、その第1弾として、イオンモール浦和美園店において滞在(通所)型の小規模デイサービス「シニアサロン樹楽イオン浦和美園店」を11月1日(木)にオープンした。
「シニアサロン樹楽イオン浦和美園店」は、イオンモール浦和美園店にあるため、ショッピングモール自体をひとつの機能訓練の場としてとらえ、しかも買い物や映画鑑賞など楽しく過ごすことができる利点がある。また、イオンモール浦和美園店はキッズパークに併設されているため、利用者と子どもたちとのふれあう機会が多くなることなどが期待される。
【シニアサロン樹楽イオン浦和美園店の特徴】
■ショッピングモールの中に「もうひとつの我が家」を
「地域の利用者が日中の時間を楽しく豊かに過ごしてもらうこと」を目的にした、全国でも珍しい大型ショッピングモール施設内の通所型デイサービス。ただ施設内で過ごすのではなく、イオンモール内で買い物をしたり、アミューズメントスペースで楽しんだり、映画を観賞するなど、大型ショッピングモール施設内ならではの機能訓練が可能になった。
■大規模な施設にない1人1人への個別対応を提供
大型のイオンモール内にあるが、10名定員の小規模デイサービスだ。介護サービス提供の内容も、送迎・入浴・趣味活動など、可能な限り個別対応を実施し、施設で過ごすという感覚ではなく、イオンモール内全てが日常の生活動作の向上設備と捉えて介護サービスを提供する。
■ニーズに合わせた利用時間を提供
利用者と家族の要望に合わせて9:00〜21:00までの介護サービス提供時間内に3時間〜9時間(18時以降は延長加算)の介護保険サービスを提供。送迎も利用者や家族の都合に合わせた時間帯での送迎が可能。
■キッズとのふれあいの場を提供
シニアサロン樹楽イオン浦和美園店はアミューズメント施設「新宝島」内にある。キッズパークに併設施設なので、孫のような子どもたちとのふれあいが出来る。
◎株式会社UCO
◎株式会社アクロス

(ケアマネジメントオンライン 2012/11/07 09:00 配信)
大型ショッピングモールを中心に、アミューズメント施設を全国に展開している株式会社UCOと全国にデイサービス「樹楽」、複合カフェ「コミックバスター」を展開している株式会社アクロスは、業務提携し、その第1弾として、イオンモール浦和美園店において滞在(通所)型の小規模デイサービス「シニアサロン樹楽イオン浦和美園店」を11月1日(木)にオープンした。
「シニアサロン樹楽イオン浦和美園店」は、イオンモール浦和美園店にあるため、ショッピングモール自体をひとつの機能訓練の場としてとらえ、しかも買い物や映画鑑賞など楽しく過ごすことができる利点がある。また、イオンモール浦和美園店はキッズパークに併設されているため、利用者と子どもたちとのふれあう機会が多くなることなどが期待される。
【シニアサロン樹楽イオン浦和美園店の特徴】
■ショッピングモールの中に「もうひとつの我が家」を
「地域の利用者が日中の時間を楽しく豊かに過ごしてもらうこと」を目的にした、全国でも珍しい大型ショッピングモール施設内の通所型デイサービス。ただ施設内で過ごすのではなく、イオンモール内で買い物をしたり、アミューズメントスペースで楽しんだり、映画を観賞するなど、大型ショッピングモール施設内ならではの機能訓練が可能になった。
■大規模な施設にない1人1人への個別対応を提供
大型のイオンモール内にあるが、10名定員の小規模デイサービスだ。介護サービス提供の内容も、送迎・入浴・趣味活動など、可能な限り個別対応を実施し、施設で過ごすという感覚ではなく、イオンモール内全てが日常の生活動作の向上設備と捉えて介護サービスを提供する。
■ニーズに合わせた利用時間を提供
利用者と家族の要望に合わせて9:00〜21:00までの介護サービス提供時間内に3時間〜9時間(18時以降は延長加算)の介護保険サービスを提供。送迎も利用者や家族の都合に合わせた時間帯での送迎が可能。
■キッズとのふれあいの場を提供
シニアサロン樹楽イオン浦和美園店はアミューズメント施設「新宝島」内にある。キッズパークに併設施設なので、孫のような子どもたちとのふれあいが出来る。
◎株式会社UCO
◎株式会社アクロス

2012年11月14日
介護キャリア段位、被災地で先行実施・・・
おはようございます。熊本の益田です
今週は、居宅訪問を中心にした営業週間です。
「如何にうまく喋るか!」ではなく「如何にたくさん喋ってもらえるか!」を目標に
張り切ってまいりたいと思います
それでは業界ネタを一つ!
『介護キャリア段位、被災地で先行実施- 内閣府、年明けから事業開始へ 』
(キャリアブレイン 2012年11月06日 12:26 )
内閣府は、介護人材の能力を、7段階で評価する「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」のレベル認定を、東日本大震災で被災した岩手・宮城・福島の3県で先行実施することを決めた。復興事業の一環としての先行実施で、年明けには、介護人材の能力を見極める「アセッサー(評価者)」育成のための研修が始まり、来年中には、初の段位認定者が誕生する見込み。
制度を運営する実施機関には、シルバーサービス振興会が内定しており、介護職の段位の認定のほか、アセッサーの講習や、アセッサーの評価を審査する外部評価機関の選定、外部評価機関の審査員の養成などを予定。先行実施では、大多数の介護人材が該当するとみられるレベル4までの認定を行う見通し。認定のための手数料は、「被災地での先行実施であることから、1人あたり3400円程度になる見込み」(内閣府)という。
「キャリア段位制度」は、業界全体で活用できる能力の「ものさし」を作ることで、効率的な人材育成と新たな人材の参入促進を目指す制度で、特に実践的スキルを重点的に評価する。段位を認定する際には、事業所の中からアセッサーを選出しなければならない。アセッサーとなる人は、一定の能力があることに加え、定められた講習を受講する必要がある。
内閣府では、14年度までに2万人、20年度までには13万人を認定する目標を掲げている。来年度の認定については、「被災3県では継続して実施する。他の地域に拡大するかどうかは、今回の先行実施の結果を受けて、検討する」(内閣府)としている。【多●正芳、●は木へんに朶】


今週は、居宅訪問を中心にした営業週間です。
「如何にうまく喋るか!」ではなく「如何にたくさん喋ってもらえるか!」を目標に
張り切ってまいりたいと思います

それでは業界ネタを一つ!
『介護キャリア段位、被災地で先行実施- 内閣府、年明けから事業開始へ 』
(キャリアブレイン 2012年11月06日 12:26 )
内閣府は、介護人材の能力を、7段階で評価する「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」のレベル認定を、東日本大震災で被災した岩手・宮城・福島の3県で先行実施することを決めた。復興事業の一環としての先行実施で、年明けには、介護人材の能力を見極める「アセッサー(評価者)」育成のための研修が始まり、来年中には、初の段位認定者が誕生する見込み。
制度を運営する実施機関には、シルバーサービス振興会が内定しており、介護職の段位の認定のほか、アセッサーの講習や、アセッサーの評価を審査する外部評価機関の選定、外部評価機関の審査員の養成などを予定。先行実施では、大多数の介護人材が該当するとみられるレベル4までの認定を行う見通し。認定のための手数料は、「被災地での先行実施であることから、1人あたり3400円程度になる見込み」(内閣府)という。
「キャリア段位制度」は、業界全体で活用できる能力の「ものさし」を作ることで、効率的な人材育成と新たな人材の参入促進を目指す制度で、特に実践的スキルを重点的に評価する。段位を認定する際には、事業所の中からアセッサーを選出しなければならない。アセッサーとなる人は、一定の能力があることに加え、定められた講習を受講する必要がある。
内閣府では、14年度までに2万人、20年度までには13万人を認定する目標を掲げている。来年度の認定については、「被災3県では継続して実施する。他の地域に拡大するかどうかは、今回の先行実施の結果を受けて、検討する」(内閣府)としている。【多●正芳、●は木へんに朶】

2012年11月13日
運営の課題は「利用者の確保」が半数以上・・・
『運営の課題は「利用者の確保」が半数以上——都内初・サービス付き高齢者向け住宅の調査』
(ケアマネジメントオンライン 2012/11/05 09:00 配信)
東京都社会福祉協議会は、2011年10月に始まったサービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住)が都内で100を超える登録がされていることを受けてアンケート調査を実施、このほどその結果を発表した。
同調査は、サ高住の普及やサービスの質の向上を目指し、その状況を明らかにすることを目的に行われた。回答が得られたのは、調査票を送付した81カ所中37カ所で、サ高住の主な対象は自立〜中程度であること、介護事業所を併設する高齢者住宅が目立つことなどが明らかに。
また、運営の課題では「利用者の確保」が半数以上で、今後、サ高住を「増やしていく予定」が3割にとどまったのも、利用者の確保が大きなネックになっていると言えそうだ。
【調査の概要】
■対 象:都内サービス付き高齢者向け住宅81カ所(8月20日現在、登録されている高齢者住宅102 カ所で、建設中の21 カ所を除く)
■調査期間 :2012年8月21日〜9月12日
■方 法 :郵送による送付、FAXによる回収
■回収状況 :37 カ所/81 カ所(回収率45.6%)
主な調査の結果は以下の通り。
■運営主体の7割が介護・福祉事業者
サ高住を運営する法人の主な業種は、70.3%が「介護・福祉」。「医療」が10.8%で、「不動産」は8.1%と1割に満たない状況だった。また、法人種別とクロス集計すると、約半数(48.6%)が介護・福祉事業を行っている株式会社が高齢者住宅を運営していた。
■賃料は6 万8,000 円〜39 万1,000 円
賃料として「家賃「管理費」と「生活支援サービス費(安否確認と生活相談サービスの費用)」を合計した金額について質問した。
サ高住では、賃料設定を複数にしている場合もあるため、最も低い賃料と最も高い賃料についてたずねたところ、最も低い賃料の平均は12 万7,561 円、最も高い賃料の平均が15 万3,872 円で、13 万〜15 万というのがサ高住の相場と言える。
しかし、最も低い賃料を設定していたサ高住では6 万8,000 円、最も高い賃料を設定していたサ高住は39 万1,000 円となっており、バラツキが極めて大きい状況だった(ただし、賃料が高いところは2人用の可能性もある)。
■居室の広さは18 平方メートル〜58.8 平方メートル
居室の広さについては、1つの建物の中に複数の居室の広さがあるサ高住もあるので、住宅の中で最も狭い居室面積と最も広い居室面積についてたずねたところ、一番狭い居室の平均が25.1 平方メートルで、サ高住の登録基準(原則)25 平方メートルとほぼ同様だった。一方、一番広い居室の平均は32.6 平方メートルだった。
また、調査の中で最も狭い居室だったのは18 平方メートルで、サ高住の登録に関して、「居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」に認められる最も狭い居室面積である。
今回の調査では、原則居室面積の25平方メートルを満たしていない高齢者住宅は12 カ所で、回答のあったサ高住の32.4%。東京のような都市部においては、25 平方メートルを確保するのが難しいことが想像できる。
■サ高住の入居者像は、要介護度「自立〜中程度」
サ高住の入居者像では、「要介護度が高い」が11.4%となり、「特に対象を決めていない」を合わせても4割程度となっている。一方、自立や軽度は8割、中程度は7割で、サ高住の主な対象は自立〜中程度までと言える。
■介護事業所を併設するサ高住が目立つ
併設事業所については、デイサービスが4割(40.5%)、訪問介護が4割弱(37.8%)、居宅介護支援事業所が3割(29.7%)だった。医療系では、診療所が2割弱(16.2%)、訪問看護が1割未満(5.4%)と少なく、病院や通所リハとの併設はないなど、介護系の事業所との併設が目立った。
■運営の課題「利用者の確保」が半数以上
運営の課題では、「利用者の確保」との回答が最も多く、半数以上(54.1%)。次いで多かったのが「職員の確保」で43.2%。制度が始まってまだ1年しか経過していないこともあり、自由記述では、一般市民へのサ高住のPRや普及啓発が課題となっているという回答も見られた。
■今後、サ高住を「増やしていく予定」は3割
今後、サ高住を増やしていくかという設問では、「増やしていく予定」が3割(35.1%)にとどまっており、「未定」が54.1%と最も多かった。一方、明確に「増やさない予定」としているのは1割(10.8%)だった。「増やさない予定」と回答した理由としては、「安定した収益がないため」「経営上無理」といった運営資金面での課題が多く、「利用者の確保」が大きなネックになっていると考えられる。
◎東京都社会福祉協議会

(ケアマネジメントオンライン 2012/11/05 09:00 配信)
東京都社会福祉協議会は、2011年10月に始まったサービス付き高齢者向け住宅(以下サ高住)が都内で100を超える登録がされていることを受けてアンケート調査を実施、このほどその結果を発表した。
同調査は、サ高住の普及やサービスの質の向上を目指し、その状況を明らかにすることを目的に行われた。回答が得られたのは、調査票を送付した81カ所中37カ所で、サ高住の主な対象は自立〜中程度であること、介護事業所を併設する高齢者住宅が目立つことなどが明らかに。
また、運営の課題では「利用者の確保」が半数以上で、今後、サ高住を「増やしていく予定」が3割にとどまったのも、利用者の確保が大きなネックになっていると言えそうだ。
【調査の概要】
■対 象:都内サービス付き高齢者向け住宅81カ所(8月20日現在、登録されている高齢者住宅102 カ所で、建設中の21 カ所を除く)
■調査期間 :2012年8月21日〜9月12日
■方 法 :郵送による送付、FAXによる回収
■回収状況 :37 カ所/81 カ所(回収率45.6%)
主な調査の結果は以下の通り。
■運営主体の7割が介護・福祉事業者
サ高住を運営する法人の主な業種は、70.3%が「介護・福祉」。「医療」が10.8%で、「不動産」は8.1%と1割に満たない状況だった。また、法人種別とクロス集計すると、約半数(48.6%)が介護・福祉事業を行っている株式会社が高齢者住宅を運営していた。
■賃料は6 万8,000 円〜39 万1,000 円
賃料として「家賃「管理費」と「生活支援サービス費(安否確認と生活相談サービスの費用)」を合計した金額について質問した。
サ高住では、賃料設定を複数にしている場合もあるため、最も低い賃料と最も高い賃料についてたずねたところ、最も低い賃料の平均は12 万7,561 円、最も高い賃料の平均が15 万3,872 円で、13 万〜15 万というのがサ高住の相場と言える。
しかし、最も低い賃料を設定していたサ高住では6 万8,000 円、最も高い賃料を設定していたサ高住は39 万1,000 円となっており、バラツキが極めて大きい状況だった(ただし、賃料が高いところは2人用の可能性もある)。
■居室の広さは18 平方メートル〜58.8 平方メートル
居室の広さについては、1つの建物の中に複数の居室の広さがあるサ高住もあるので、住宅の中で最も狭い居室面積と最も広い居室面積についてたずねたところ、一番狭い居室の平均が25.1 平方メートルで、サ高住の登録基準(原則)25 平方メートルとほぼ同様だった。一方、一番広い居室の平均は32.6 平方メートルだった。
また、調査の中で最も狭い居室だったのは18 平方メートルで、サ高住の登録に関して、「居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」に認められる最も狭い居室面積である。
今回の調査では、原則居室面積の25平方メートルを満たしていない高齢者住宅は12 カ所で、回答のあったサ高住の32.4%。東京のような都市部においては、25 平方メートルを確保するのが難しいことが想像できる。
■サ高住の入居者像は、要介護度「自立〜中程度」
サ高住の入居者像では、「要介護度が高い」が11.4%となり、「特に対象を決めていない」を合わせても4割程度となっている。一方、自立や軽度は8割、中程度は7割で、サ高住の主な対象は自立〜中程度までと言える。
■介護事業所を併設するサ高住が目立つ
併設事業所については、デイサービスが4割(40.5%)、訪問介護が4割弱(37.8%)、居宅介護支援事業所が3割(29.7%)だった。医療系では、診療所が2割弱(16.2%)、訪問看護が1割未満(5.4%)と少なく、病院や通所リハとの併設はないなど、介護系の事業所との併設が目立った。
■運営の課題「利用者の確保」が半数以上
運営の課題では、「利用者の確保」との回答が最も多く、半数以上(54.1%)。次いで多かったのが「職員の確保」で43.2%。制度が始まってまだ1年しか経過していないこともあり、自由記述では、一般市民へのサ高住のPRや普及啓発が課題となっているという回答も見られた。
■今後、サ高住を「増やしていく予定」は3割
今後、サ高住を増やしていくかという設問では、「増やしていく予定」が3割(35.1%)にとどまっており、「未定」が54.1%と最も多かった。一方、明確に「増やさない予定」としているのは1割(10.8%)だった。「増やさない予定」と回答した理由としては、「安定した収益がないため」「経営上無理」といった運営資金面での課題が多く、「利用者の確保」が大きなネックになっていると考えられる。
◎東京都社会福祉協議会

2012年11月12日
「公的介護保険」と「民間介護保険」 一体何が違う?
(All About :2012年10月16日)嵯峨崎 泰子
家族や自分自身が介護を受ける立場にならないと、介護保険の中身はよくわかりません。いずれやってくる超高齢化社会に備え、介護保険の仕組み、制度、保障内容などをここで理解しておきましょう。
公的介護保険とは?

65歳以上しか受給できないイメージの公的介護保険だが、対象は実は40歳以上
公的介護保険の被保険者は、市町村内に住所のある医療保険の加入者(国保、社保)。被保険者は次の2つに区分されます。
■第1号被保険者65歳以上の人。要支援、要介護状態になったとき、公的介護保険の介護サービスを受けることができます。
■第2号被保険者
40歳~64歳の人。加齢が原因となる特定疾病によって要支援、要介護状態になったとき、介護保険の介護サービスを受けることができます。特定疾病は、骨折による骨粗鬆症、初老期における認知症、末期がんなど、16の疾病が該当します(詳細は厚生労働省HPをご参照ください)。
いずれも要支援、要介護認定を受けたのち、公的介護保険のサービスを受けることになります。
介護保険のサービス内容と、その限界
「要支援状態」の場合、利用できるサービスは「介護予防給付」です。今後、要介護状態に進むことを予防するための給付となり、地域包括支援センターのケアマネージャーがケアプランを作成します。
「要介護状態」の場合、利用できるサービスは「介護給付」です。自宅で生活しながら施設を利用、施設に入所、介護の環境を整えるなど、サービスは多種多様で、居宅介護支援事業者に配備されているケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランに従い、介護サービスを受けると被保険者は「費用1割負担」が基本となりますが、保険ではまかないきれない費用もあります。例えば、食費、介護タクシーの利用、おむつ、レクリエーション代などです。これらのお金は意外と無視できず、長期間にわたって続き、大きな負担になっていきます。
現場から見た「公的介護保険はココが足りない」
要支援、要介護の認定を受けた人は、在宅で介護サービスを受けたり、特養やグループホームなどの施設を利用します。その様々な場面で、介護保険ではまかなえない自己負担が発生します。
例を挙げると、施設に通いデイサービスなどのサービスを受ける場合、食費、レクリエーション費、(状態によって)おむつ費用が必要となります。特養などの施設に入所した場合も、食費や居住費が必要になります。最近の特養は個室タイプのユニット型が主流になっており、居住費はかなり高額になっています。訪問・通所サービスの際、通常の営業地域外に該当すれば、サービス利用時の交通費も必要に。通院時に介護タクシーを利用し、それが車椅子などを搬入できるストレッチャー仕様の特別車になると、往復で1万円程度はすぐにいってしまいます。
また、団塊の世代は都会に出てきている人が多く、親が要介護状態になると遠距離介護になります。親元に帰る際、飛行機の介護割引なども利用できますが、負担ゼロにはなりません。これらはすべて公的介護保険でまかなえない費用です。
>>民間介護保険は一体何がカバーできる?
家族や自分自身が介護を受ける立場にならないと、介護保険の中身はよくわかりません。いずれやってくる超高齢化社会に備え、介護保険の仕組み、制度、保障内容などをここで理解しておきましょう。
公的介護保険とは?

65歳以上しか受給できないイメージの公的介護保険だが、対象は実は40歳以上
公的介護保険の被保険者は、市町村内に住所のある医療保険の加入者(国保、社保)。被保険者は次の2つに区分されます。
■第1号被保険者65歳以上の人。要支援、要介護状態になったとき、公的介護保険の介護サービスを受けることができます。
■第2号被保険者
40歳~64歳の人。加齢が原因となる特定疾病によって要支援、要介護状態になったとき、介護保険の介護サービスを受けることができます。特定疾病は、骨折による骨粗鬆症、初老期における認知症、末期がんなど、16の疾病が該当します(詳細は厚生労働省HPをご参照ください)。
いずれも要支援、要介護認定を受けたのち、公的介護保険のサービスを受けることになります。
介護保険のサービス内容と、その限界
「要支援状態」の場合、利用できるサービスは「介護予防給付」です。今後、要介護状態に進むことを予防するための給付となり、地域包括支援センターのケアマネージャーがケアプランを作成します。
「要介護状態」の場合、利用できるサービスは「介護給付」です。自宅で生活しながら施設を利用、施設に入所、介護の環境を整えるなど、サービスは多種多様で、居宅介護支援事業者に配備されているケアマネージャーがケアプランを作成します。
ケアプランに従い、介護サービスを受けると被保険者は「費用1割負担」が基本となりますが、保険ではまかないきれない費用もあります。例えば、食費、介護タクシーの利用、おむつ、レクリエーション代などです。これらのお金は意外と無視できず、長期間にわたって続き、大きな負担になっていきます。
現場から見た「公的介護保険はココが足りない」
要支援、要介護の認定を受けた人は、在宅で介護サービスを受けたり、特養やグループホームなどの施設を利用します。その様々な場面で、介護保険ではまかなえない自己負担が発生します。
例を挙げると、施設に通いデイサービスなどのサービスを受ける場合、食費、レクリエーション費、(状態によって)おむつ費用が必要となります。特養などの施設に入所した場合も、食費や居住費が必要になります。最近の特養は個室タイプのユニット型が主流になっており、居住費はかなり高額になっています。訪問・通所サービスの際、通常の営業地域外に該当すれば、サービス利用時の交通費も必要に。通院時に介護タクシーを利用し、それが車椅子などを搬入できるストレッチャー仕様の特別車になると、往復で1万円程度はすぐにいってしまいます。
また、団塊の世代は都会に出てきている人が多く、親が要介護状態になると遠距離介護になります。親元に帰る際、飛行機の介護割引なども利用できますが、負担ゼロにはなりません。これらはすべて公的介護保険でまかなえない費用です。
>>民間介護保険は一体何がカバーできる?
2012年11月04日
10人に1人が認知症になる覚悟を・・・・
『「10人に1人が認知症になる覚悟を」- 厚労省・迫井課長 』
(キャリアブレイン 2012年10月29日 15:24 )
厚生労働省老健局老人保健課の迫井正深課長はこのほど、保健・医療・福祉サービス研究会が主催する老人保健施設(老健)をテーマとしたセミナーで講演した。迫井課長は、今後、認知症は極めて重要なテーマとなるとした上で、「日本社会全体が『10人に1人は認知症になる』という覚悟を固める必要がある」と訴えた。

「日本社会全体が『10人に1人は認知症になる』という覚悟を固める必要がある」と述べる迫井課長(東京都内)
また、ケアマネジメントの質向上も今後の重要なテーマと指摘。「1人ひとりのケアマネジャーの資質を向上させる工夫と同時に、ケアマネジメントの質を向上させるための仕組みの整備も大切」と述べた上で、具体的には、地域ケア会議をどのように位置づけるかが重要になるとの認識を示した。
今年4月、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)や複合型サービスが導入された点については、「(団塊の世代が後期高齢者となる)2025年を目指した最初の一歩」とする一方、より実情にあったサービスを実現するため、継続して改善に取り組む必要があるとも述べた。
老健については、「医療サービスの充実が今後の課題」と指摘。また、今年4月の介護報酬改定で、短期集中リハビリテーション実施加算やターミナルケア加算の報酬や要件が見直された点に触れた上で、看取りや在宅復帰を目指したリハビリへの老健の積極的な取り組みが期待されるとした。【多●正芳、●は木へんに朶】
(キャリアブレイン 2012年10月29日 15:24 )
厚生労働省老健局老人保健課の迫井正深課長はこのほど、保健・医療・福祉サービス研究会が主催する老人保健施設(老健)をテーマとしたセミナーで講演した。迫井課長は、今後、認知症は極めて重要なテーマとなるとした上で、「日本社会全体が『10人に1人は認知症になる』という覚悟を固める必要がある」と訴えた。

「日本社会全体が『10人に1人は認知症になる』という覚悟を固める必要がある」と述べる迫井課長(東京都内)
また、ケアマネジメントの質向上も今後の重要なテーマと指摘。「1人ひとりのケアマネジャーの資質を向上させる工夫と同時に、ケアマネジメントの質を向上させるための仕組みの整備も大切」と述べた上で、具体的には、地域ケア会議をどのように位置づけるかが重要になるとの認識を示した。
今年4月、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)や複合型サービスが導入された点については、「(団塊の世代が後期高齢者となる)2025年を目指した最初の一歩」とする一方、より実情にあったサービスを実現するため、継続して改善に取り組む必要があるとも述べた。
老健については、「医療サービスの充実が今後の課題」と指摘。また、今年4月の介護報酬改定で、短期集中リハビリテーション実施加算やターミナルケア加算の報酬や要件が見直された点に触れた上で、看取りや在宅復帰を目指したリハビリへの老健の積極的な取り組みが期待されるとした。【多●正芳、●は木へんに朶】
2012年11月03日
「科学的介護と地域貢献活動の推進を」- 全国老施協・中田会長
(キャリアブレイン 2012年10月23日 19:29)
全国老人福祉施設大会が23日、広島市内で開幕した。全国老人福祉施設協議会(全国老施協)の中田清会長は講演で、住居とケアの提供が一体となっている特別養護老人ホーム(特養)こそ、地域包括ケアシステムの拠点として活動すべきと改めて強調。そのためにも、エビデンスに基づいた「科学的介護」を普及させる必要があると訴えた。さらに、社会福祉法人が低所得者の利用者負担を軽減する「社会福祉法人減免制度」(社福減免)をはじめとした地域貢献活動について、「各法人はさらに積極的に挑戦してほしい」と呼び掛けた。

全国老人福祉施設大会で講演する中田会長(23日、広島市内)
中田会長は、地域包括ケアについて「実現は極めて難しいという声が現場では圧倒的」と述べた。ただ、地域包括ケアの考え方そのものを「否定するものではない」とした上で、住居とケアが一体となっている特養が、地域包括ケアの拠点として機能すべきと訴えた。
また、制度改正や介護報酬改定を通じ、政策の流れは施設から在宅へとかじが切られているとし、「その流れを『施設も在宅も大切』に変える必要がある」と指摘。そのためには、「施設だからこそできるケアのエビデンスを確立し、科学的介護を全国津々浦々の施設で実践する必要がある」と訴えた。具体的な取り組みとしては、認知症ケアなどの方法を見直すことや、看取りや口腔ケアの積極的な実施などを挙げた。
■社福減免「すべての施設で」
社福減免については、「財務省から、社福減免を導入していない施設ほど内部留保が大きいという指摘があった」と言及。社福減免への取り組みが不十分なままでは、社会福祉法人への課税の是非が論じられる可能性もあるとした上で、「(社福減免は)100%、すべての施設がやらなければならない」と訴えた。さらに、社福減免も含めた地域貢献活動についても、「当然、やるべきこと」と強調。具体的な活動として、保育園や子育て支援センター、学童保育などを挙げた。
■内部留保「入所者が納得する説明を」-自民・中村参院議員
全国老施協常任顧問の中村博彦・自民党参院議員は来賓あいさつで、「介護保険が成立した後、現場の実情を無視して制度がつくられてきた感がある」と、現状の制度設計の在り方を批判。社会保障制度改革の在り方を議論する国民会議について、「そのメンバーには、弱者の立場を考えることができる人が選ばれなければならない」と述べた。その一方で、「わたしたちも変わらなければならない。天下りした施設長が、のんべんだらりと運営する時代ではない」とし、特に1施設当たり3億円はあるとされる内部留保については「入所者が納得できる説明をすることが大切」と訴えた。【多●正芳、●は木へんに朶】
全国老人福祉施設大会が23日、広島市内で開幕した。全国老人福祉施設協議会(全国老施協)の中田清会長は講演で、住居とケアの提供が一体となっている特別養護老人ホーム(特養)こそ、地域包括ケアシステムの拠点として活動すべきと改めて強調。そのためにも、エビデンスに基づいた「科学的介護」を普及させる必要があると訴えた。さらに、社会福祉法人が低所得者の利用者負担を軽減する「社会福祉法人減免制度」(社福減免)をはじめとした地域貢献活動について、「各法人はさらに積極的に挑戦してほしい」と呼び掛けた。

全国老人福祉施設大会で講演する中田会長(23日、広島市内)
中田会長は、地域包括ケアについて「実現は極めて難しいという声が現場では圧倒的」と述べた。ただ、地域包括ケアの考え方そのものを「否定するものではない」とした上で、住居とケアが一体となっている特養が、地域包括ケアの拠点として機能すべきと訴えた。
また、制度改正や介護報酬改定を通じ、政策の流れは施設から在宅へとかじが切られているとし、「その流れを『施設も在宅も大切』に変える必要がある」と指摘。そのためには、「施設だからこそできるケアのエビデンスを確立し、科学的介護を全国津々浦々の施設で実践する必要がある」と訴えた。具体的な取り組みとしては、認知症ケアなどの方法を見直すことや、看取りや口腔ケアの積極的な実施などを挙げた。
■社福減免「すべての施設で」
社福減免については、「財務省から、社福減免を導入していない施設ほど内部留保が大きいという指摘があった」と言及。社福減免への取り組みが不十分なままでは、社会福祉法人への課税の是非が論じられる可能性もあるとした上で、「(社福減免は)100%、すべての施設がやらなければならない」と訴えた。さらに、社福減免も含めた地域貢献活動についても、「当然、やるべきこと」と強調。具体的な活動として、保育園や子育て支援センター、学童保育などを挙げた。
■内部留保「入所者が納得する説明を」-自民・中村参院議員
全国老施協常任顧問の中村博彦・自民党参院議員は来賓あいさつで、「介護保険が成立した後、現場の実情を無視して制度がつくられてきた感がある」と、現状の制度設計の在り方を批判。社会保障制度改革の在り方を議論する国民会議について、「そのメンバーには、弱者の立場を考えることができる人が選ばれなければならない」と述べた。その一方で、「わたしたちも変わらなければならない。天下りした施設長が、のんべんだらりと運営する時代ではない」とし、特に1施設当たり3億円はあるとされる内部留保については「入所者が納得できる説明をすることが大切」と訴えた。【多●正芳、●は木へんに朶】
2012年11月02日
『デイサービス、ショートステイが介護負担を軽減する・・・
『デイサービス、ショートステイが介護負担を軽減する――明治安田生命/介護生活の意識調査』
(ケアマネジメントオンライン 2012/10/16 12:00 配信)
明治安田生命福祉研究所は、「介護生活の実態と意識に関する調査」を実施し、その結果を発表した。
同調査は、2012年6月、家族等の介護経験がある全国の40~70歳代の男女1,032名を対象に、介護サービスの利用実態や経済的な側面、さらに介護に関する意識に焦点をあてた調査をインターネットで実施したもの。
主な内容としては、以下の結果が出ている。
【利用経験のある公的介護保険サービス】⇒ デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ
6割が「デイサービス」、4割が「ホームヘルプ」を利用。夜間の介護負担から解放される「ショートステイ」も3人に1人が利用している。
【公的介護保険の利用限度額の消化状況】⇒限度額いっぱいの利用者は4割
限度額いっぱいまで利用している人は4割に留まる。限度額まで利用しない人のうち半数が「利用しなくても十分なサービスを受けられている」「できるだけ身内で介護したい」とする一方、2割の人が「これ以上の自己負担は難しい」という理由を挙げている。
【「上乗せサービス」の利用状況】⇒4人に1人が経験あり
4人に1人が、上乗せサービスを利用した経験があった。利用したサービスとしては「デイサービス」「ショートステイ」が多く、どちらも在宅で介護している人がひとときの間、介護からの解放が得られるものである。この結果から、費用を支払うことが可能であれば、これらのサービスが介護負担軽減につながることを示している。
【介護のためのリフォーム】⇒半数強が実施
介護経験者の半数強がリフォームを実施。通常30万円前後かかるトイレの洋式化を2.5割が実施し、さらに高額な費用が想定される浴槽の交換を1.6割の人が実施していた。かかった費用は3割が10万円未満である一方、1割は総費用100万円以上かかっており(ただし、支払った金額ではない)、介護が必要になった場合、それなりにまとまったリフォーム費用がかかる可能性があることもわかってきた。
【もっとお金があれば利用したいサービス】⇒リフォームのトップは浴槽交換
介護経験者の3人に2人が、もっとお金に余裕があれば利用したいサービスがあると答えている。希望する内容は、訪問介護などの在宅サービスの利用を増やす、ショートステイの利用を増やす、有料老人ホームへの入居、デイサービスの利用を増やす、といった項目がそれぞれ2割以上見られた。リフォームへの希望も1.6割あり、そのトップは公的介護保険での女性の対象外である「浴槽交換」だった。また、車いす用に廊下を拡張したいという回答も高い割合を示していた。
【介護の苦労】⇒9割の介護経験者が実感 介護経験者の9割が介護の苦労を実感しており、「負担を軽くするためには事前の資金準備が重要」だと感じている。最も多かった苦労は「精神的負担」で男女とも4人に3人が挙げている。
【就労・収入への影響】⇒4人に1人に働き方に変化あり 介護経験者の4人に1人が、介護にあたり働き方に変化があり、2割強の世帯は収入が減少している。半分以下に減った世帯も1割強いて、退職など大幅な収入減少を伴う変化があったことがうかがえる。
【介護への準備】⇒約半数が準備をしていた
介護経験者の約半数が、介護を始める前に、情報の収集、介護について親族と相談、家のリフォームなど、何らかの準備をしていた。介護を始める前に準備しておいたらよかったこととしては、「実際の介護の技術や知識」(26.7%)、「公的介護保険制度に関する知識」(25.1%)、「介護費用の蓄え」(23.5%)、「(介護相手の)民間の介護保険等への加入」(12.1%)を挙げている。
◎明治安田生命生活福祉研究所
ちなみに記事中段の「トップは公的介護保険での女性の対象外である「浴槽交換」だった。の女性→助成の間違いですね そして、
そして、
熊本市では「浴槽交換」を段差解消工事として公的介護保険の対象として認めています。
ご相談の際は、ふくえん熊本(096-285-7586)まで

(ケアマネジメントオンライン 2012/10/16 12:00 配信)
明治安田生命福祉研究所は、「介護生活の実態と意識に関する調査」を実施し、その結果を発表した。
同調査は、2012年6月、家族等の介護経験がある全国の40~70歳代の男女1,032名を対象に、介護サービスの利用実態や経済的な側面、さらに介護に関する意識に焦点をあてた調査をインターネットで実施したもの。
主な内容としては、以下の結果が出ている。
【利用経験のある公的介護保険サービス】⇒ デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ
6割が「デイサービス」、4割が「ホームヘルプ」を利用。夜間の介護負担から解放される「ショートステイ」も3人に1人が利用している。
【公的介護保険の利用限度額の消化状況】⇒限度額いっぱいの利用者は4割
限度額いっぱいまで利用している人は4割に留まる。限度額まで利用しない人のうち半数が「利用しなくても十分なサービスを受けられている」「できるだけ身内で介護したい」とする一方、2割の人が「これ以上の自己負担は難しい」という理由を挙げている。
【「上乗せサービス」の利用状況】⇒4人に1人が経験あり
4人に1人が、上乗せサービスを利用した経験があった。利用したサービスとしては「デイサービス」「ショートステイ」が多く、どちらも在宅で介護している人がひとときの間、介護からの解放が得られるものである。この結果から、費用を支払うことが可能であれば、これらのサービスが介護負担軽減につながることを示している。
【介護のためのリフォーム】⇒半数強が実施
介護経験者の半数強がリフォームを実施。通常30万円前後かかるトイレの洋式化を2.5割が実施し、さらに高額な費用が想定される浴槽の交換を1.6割の人が実施していた。かかった費用は3割が10万円未満である一方、1割は総費用100万円以上かかっており(ただし、支払った金額ではない)、介護が必要になった場合、それなりにまとまったリフォーム費用がかかる可能性があることもわかってきた。
【もっとお金があれば利用したいサービス】⇒リフォームのトップは浴槽交換
介護経験者の3人に2人が、もっとお金に余裕があれば利用したいサービスがあると答えている。希望する内容は、訪問介護などの在宅サービスの利用を増やす、ショートステイの利用を増やす、有料老人ホームへの入居、デイサービスの利用を増やす、といった項目がそれぞれ2割以上見られた。リフォームへの希望も1.6割あり、そのトップは公的介護保険での女性の対象外である「浴槽交換」だった。また、車いす用に廊下を拡張したいという回答も高い割合を示していた。
【介護の苦労】⇒9割の介護経験者が実感 介護経験者の9割が介護の苦労を実感しており、「負担を軽くするためには事前の資金準備が重要」だと感じている。最も多かった苦労は「精神的負担」で男女とも4人に3人が挙げている。
【就労・収入への影響】⇒4人に1人に働き方に変化あり 介護経験者の4人に1人が、介護にあたり働き方に変化があり、2割強の世帯は収入が減少している。半分以下に減った世帯も1割強いて、退職など大幅な収入減少を伴う変化があったことがうかがえる。
【介護への準備】⇒約半数が準備をしていた
介護経験者の約半数が、介護を始める前に、情報の収集、介護について親族と相談、家のリフォームなど、何らかの準備をしていた。介護を始める前に準備しておいたらよかったこととしては、「実際の介護の技術や知識」(26.7%)、「公的介護保険制度に関する知識」(25.1%)、「介護費用の蓄え」(23.5%)、「(介護相手の)民間の介護保険等への加入」(12.1%)を挙げている。
◎明治安田生命生活福祉研究所
ちなみに記事中段の「トップは公的介護保険での女性の対象外である「浴槽交換」だった。の女性→助成の間違いですね
 そして、
そして、熊本市では「浴槽交換」を段差解消工事として公的介護保険の対象として認めています。
ご相談の際は、ふくえん熊本(096-285-7586)まで


2012年11月01日
ケアマネは「プロ」ではなく「制度内スペシャリスト」
おはようございます。ふくえん熊本の益田です(^.^)
今日から11月に突入します。今年も残り2ヵ月を切りました。早すぎです(^_^;)
今年の初めに立てた目標を達成できるように、ラストスパートをかけていきたいと思います
それではヒートアップ気味の業界ネタを一つ・・・・
『ケアマネは「プロ」ではなく「制度内スペシャリスト」――第6回ケアマネのあり方検討会レポ(2)』
(ケアマネジメントオンライン 2012/10/15 12:00 配信)
10月10日、東京・虎ノ門で厚生労働省の「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の第6回会合が開かれた。
当日は事務局から示された検討すべき課題、課題への対応の方向性(当日の配布資料はこちら)をもとに、前回とは打って変わって活発な議論が行われた。ここでは、「地域ケア会議」についての意見交換を紹介した1回目に続き、それ以外の議論をいくつか紹介する。
OJTによる研修のあり方
前回、藤井賢一郎氏(日本社会事業大学専門職大学院准教授)から、「インターンシップ」という表現で、ケアマネ資格取得前に現場で実践的研修を行ってはという提案があった。今回の資料にこの提案が載ってこなかったことから、藤井氏は、「実現可能性が低いということではずされたのかもしれないが」と苦笑しつつ、次のように述べた。
「一つには、資格・研修制度だけではどうも人が育たないということで、地域ケア会議を通して育てていこうという視点が入ってきた。もう一つには、非定型業務は日々の仕事の繰り返しの中で業務支援を通して身につけていくもの。それが1人ケアマネ事業所などではOJTができていないのではないかと懸念されている。だから初期の段階では、きちんとOJTでの研修をしてほしいということ。つまり、達成目標を定めて、それをクリアしたことを誰かがチェックする。そういう仕組みを半年あるいは1年いれると。そうしないと人が育っていかないと考えている」と、OJTのしくみの必要性について再度訴えた。
一方、堀田聰子氏(労働政策研究・研修機構研究員)は、システムとしてのOJTだけでなく、ケアマネ同士での学びを促進するOJTの必要性について言及した。「1人前になるまでの継続的OJTに加え、さらに広い意味での継続的OJTを考えたとき、一つには多職種での話し合いの場となる地域ケア会議がある。これはいわばシステムとしてのOJT。さらに、ケアマネ間でのスーパーバイズと、協会あるいは学会など、フラットなケアマネ・コミュニティの中での日常的な振り返りが必要だと思う。ただ後者については、国はあくまでも後方支援する立場。そうしたケアマネの資質向上のための方策の全体像を描いて、システムとしてのOJTとそうでないOJTとの関係が整理されるといいと思う」と述べた。
保険者機能の強化
「資料の検討課題を見ると、『必ずしも十分ではない』という表現がたくさんある。そもそも世の中のたいていのものは不十分であり、言ってみればケアマネより保険者の方がよっぽど不十分だ」と喝破したのは、小山秀夫氏(兵庫県立大学教授)。小山氏は、「現行法では、保険者にできることは現状で精一杯。保険者機能を強化するには、法改正をしないと無理」と言いきった。
一方、筒井孝子氏(国立保険医療科学院統括研究官)は、まず、「この検討会はケアマネジメント機能を向上させる方法論を検討する場であり、機能を担う個人の質を上げる方策ではなく、ケアマネジメント機能を高めるシステム化を進める方策を考える必要がある」と検討会の目的を改めて整理。
そして、「そのシステム化の方策として挙げられているのが地域ケア会議であり、これは保険者機能を高めるための一つのツールでもある。保険者主導で地域ケア会議を開催するならば、保険者にもトップから1400番目があるわけで、トップが和光市だとすれば末位にいる保険者をどうするのか。これまで検討されていない、保険者機能を強化する方策、地域ケア会議をシステム化していく方策をここで議論して、標準化できるものはしていくことが必要なのではないか」と、議論の方向性を明示する意見を述べた。

また、水村美穂子氏(東京都青梅市地域包括支援センターすえひろセンター長)は、「未熟なケアマネを地域ケア会議でフォローする仕組みはいいと思うが、そのためには保険者の教育が必要。3年ごとに異動する担当者に介護保険についての深い理解を求めることも、そもそも継続的に良好な関係を作ることも難しい現状がある。ケアマネジャー個人の資質向上と共に、システム作りという点では保険者教育は欠かせない」と訴えた。
ケアマネは制度内スペシャリスト
議論の過程で、藤井氏から「ケアマネは専門職、プロフェッショナルだと思っているが」という言葉が出たのを受けて、小山氏が言ったのは、「ケアマネは制度内スペシャリストであって、プロフェッショナルではない」という意見。小山氏は、「これだけいろいろ言われてしまうのは、要するにプロではないから」と、またもバッサリ。そして、「プロになってほしいと期待するにしても、プロフェッショナルの専門的な技術体系の細部を法律で規定するのはおかしい。そんなことを議論しても仕方がない」と、声を大にして言い放った。
この日の議論を振り返ると、「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方」の検討会であったはずが、筒井氏から「個人のレベルアップを検討する場ではない」とされ、保険者機能を強化するには「現状では無理。法改正が必要」と小山氏に言われ、地域ケア会議の制度化については「義務化しても形骸化するだけ」と野中氏から切って捨てられるなど、示された検討課題に対して厳しい意見が多数飛んだ。それでも地域ケア会議についての様々な意見の中から、その是非はともかく、これを活用しながら保険者機能の強化とケアマネのレベルアップを図っていくというような方向性が、やや見えた検討会であった。
※厚生労働省では、この検討会で議論されている内容や、第6回で示した方向性の基本的考え方について、ケアマネ現職者などからの意見を募集中。締切は10月31日(水)まで。詳しくはこちらを!
今日から11月に突入します。今年も残り2ヵ月を切りました。早すぎです(^_^;)
今年の初めに立てた目標を達成できるように、ラストスパートをかけていきたいと思います

それではヒートアップ気味の業界ネタを一つ・・・・

『ケアマネは「プロ」ではなく「制度内スペシャリスト」――第6回ケアマネのあり方検討会レポ(2)』
(ケアマネジメントオンライン 2012/10/15 12:00 配信)
10月10日、東京・虎ノ門で厚生労働省の「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する検討会」の第6回会合が開かれた。
当日は事務局から示された検討すべき課題、課題への対応の方向性(当日の配布資料はこちら)をもとに、前回とは打って変わって活発な議論が行われた。ここでは、「地域ケア会議」についての意見交換を紹介した1回目に続き、それ以外の議論をいくつか紹介する。
OJTによる研修のあり方
前回、藤井賢一郎氏(日本社会事業大学専門職大学院准教授)から、「インターンシップ」という表現で、ケアマネ資格取得前に現場で実践的研修を行ってはという提案があった。今回の資料にこの提案が載ってこなかったことから、藤井氏は、「実現可能性が低いということではずされたのかもしれないが」と苦笑しつつ、次のように述べた。
「一つには、資格・研修制度だけではどうも人が育たないということで、地域ケア会議を通して育てていこうという視点が入ってきた。もう一つには、非定型業務は日々の仕事の繰り返しの中で業務支援を通して身につけていくもの。それが1人ケアマネ事業所などではOJTができていないのではないかと懸念されている。だから初期の段階では、きちんとOJTでの研修をしてほしいということ。つまり、達成目標を定めて、それをクリアしたことを誰かがチェックする。そういう仕組みを半年あるいは1年いれると。そうしないと人が育っていかないと考えている」と、OJTのしくみの必要性について再度訴えた。
一方、堀田聰子氏(労働政策研究・研修機構研究員)は、システムとしてのOJTだけでなく、ケアマネ同士での学びを促進するOJTの必要性について言及した。「1人前になるまでの継続的OJTに加え、さらに広い意味での継続的OJTを考えたとき、一つには多職種での話し合いの場となる地域ケア会議がある。これはいわばシステムとしてのOJT。さらに、ケアマネ間でのスーパーバイズと、協会あるいは学会など、フラットなケアマネ・コミュニティの中での日常的な振り返りが必要だと思う。ただ後者については、国はあくまでも後方支援する立場。そうしたケアマネの資質向上のための方策の全体像を描いて、システムとしてのOJTとそうでないOJTとの関係が整理されるといいと思う」と述べた。
保険者機能の強化
「資料の検討課題を見ると、『必ずしも十分ではない』という表現がたくさんある。そもそも世の中のたいていのものは不十分であり、言ってみればケアマネより保険者の方がよっぽど不十分だ」と喝破したのは、小山秀夫氏(兵庫県立大学教授)。小山氏は、「現行法では、保険者にできることは現状で精一杯。保険者機能を強化するには、法改正をしないと無理」と言いきった。
一方、筒井孝子氏(国立保険医療科学院統括研究官)は、まず、「この検討会はケアマネジメント機能を向上させる方法論を検討する場であり、機能を担う個人の質を上げる方策ではなく、ケアマネジメント機能を高めるシステム化を進める方策を考える必要がある」と検討会の目的を改めて整理。
そして、「そのシステム化の方策として挙げられているのが地域ケア会議であり、これは保険者機能を高めるための一つのツールでもある。保険者主導で地域ケア会議を開催するならば、保険者にもトップから1400番目があるわけで、トップが和光市だとすれば末位にいる保険者をどうするのか。これまで検討されていない、保険者機能を強化する方策、地域ケア会議をシステム化していく方策をここで議論して、標準化できるものはしていくことが必要なのではないか」と、議論の方向性を明示する意見を述べた。

また、水村美穂子氏(東京都青梅市地域包括支援センターすえひろセンター長)は、「未熟なケアマネを地域ケア会議でフォローする仕組みはいいと思うが、そのためには保険者の教育が必要。3年ごとに異動する担当者に介護保険についての深い理解を求めることも、そもそも継続的に良好な関係を作ることも難しい現状がある。ケアマネジャー個人の資質向上と共に、システム作りという点では保険者教育は欠かせない」と訴えた。
ケアマネは制度内スペシャリスト
議論の過程で、藤井氏から「ケアマネは専門職、プロフェッショナルだと思っているが」という言葉が出たのを受けて、小山氏が言ったのは、「ケアマネは制度内スペシャリストであって、プロフェッショナルではない」という意見。小山氏は、「これだけいろいろ言われてしまうのは、要するにプロではないから」と、またもバッサリ。そして、「プロになってほしいと期待するにしても、プロフェッショナルの専門的な技術体系の細部を法律で規定するのはおかしい。そんなことを議論しても仕方がない」と、声を大にして言い放った。
この日の議論を振り返ると、「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方」の検討会であったはずが、筒井氏から「個人のレベルアップを検討する場ではない」とされ、保険者機能を強化するには「現状では無理。法改正が必要」と小山氏に言われ、地域ケア会議の制度化については「義務化しても形骸化するだけ」と野中氏から切って捨てられるなど、示された検討課題に対して厳しい意見が多数飛んだ。それでも地域ケア会議についての様々な意見の中から、その是非はともかく、これを活用しながら保険者機能の強化とケアマネのレベルアップを図っていくというような方向性が、やや見えた検討会であった。
※厚生労働省では、この検討会で議論されている内容や、第6回で示した方向性の基本的考え方について、ケアマネ現職者などからの意見を募集中。締切は10月31日(水)まで。詳しくはこちらを!
2012年10月30日
サ高住市場、2020年には9660億円に- 富士経済が調査
おはようございます。ふくえん熊本の益田です
毎朝、10℃近くまで気温が下がりますので、すでに私の故郷、奄美大島の真冬の寒さに匹敵する環境です!熊本の冬は早くも3回目ですが、まったく慣れませんね
さて今日の業界ネタは、ある意味ビジネスチャンス しかし、
しかし、
安易に飛びつくと痛い目にあいそうな話です
記事の中段ぐらいに「継続的な運営が可能なビジネスモデルの構築こそが重要ではないか」とありますが、その通りだと思います。単発ではなく、総合的かつ継続的に相乗効果を生み出せる仕組みが必要でしょう それが難しいんでしょうけどね・・・・
それが難しいんでしょうけどね・・・・
(キャリアブレイン 2012年10月17日 14:10 )
各種市場の総合マーケティングリサーチを行う富士経済は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の市場規模について、2020年には約9660億円まで拡大するとした調査報告をまとめた。11年(68億円)の140倍を超える規模拡大が見込まれることになる。また、福祉用具レンタルサービスなどの市場については、倍以上に拡大するとしている。
富士経済では、今年6月から8月にかけて、高齢者の生活を支援する製品や介護サービスの国内市場について調査。その結果を基に20年の市場規模などについて予測した。
その結果、サ高住の市場規模(事業売上額)は約9660億円、施設数は約1万7000件に達すると予測した。制度が始まった11年と比較すると、市場規模では142.1倍、施設数では151.8倍の拡大となる。急拡大するサ高住について富士経済では、「高齢者施設の代替としての役割も期待されるだけに、参入事業者にとっては、継続的な運営が可能なビジネスモデルの構築こそが重要ではないか」としている。
また、認知症の要介護者の動作をセンサーが感知して介護者などに知らせ、徘徊や転倒を防止できるようにする「徘徊・転倒防止機器」の市場規模(メーカー販売額)については、約53億円と予測。11年(約19億円)の2.8倍近くにまで拡大するとした。その背景について、富士経済では「病院だけでなく、サ高住や有料老人ホーム、あるいは在宅での需要が高まるため」と分析している。そのほか、福祉用具レンタルサービスの市場規模(事業売上額)についても、11年(約2240億円)の倍以上となる約5260億円まで拡大すると予測している。
【多●正芳、●は木へんに朶】


毎朝、10℃近くまで気温が下がりますので、すでに私の故郷、奄美大島の真冬の寒さに匹敵する環境です!熊本の冬は早くも3回目ですが、まったく慣れませんね

さて今日の業界ネタは、ある意味ビジネスチャンス
 しかし、
しかし、安易に飛びつくと痛い目にあいそうな話です

記事の中段ぐらいに「継続的な運営が可能なビジネスモデルの構築こそが重要ではないか」とありますが、その通りだと思います。単発ではなく、総合的かつ継続的に相乗効果を生み出せる仕組みが必要でしょう
 それが難しいんでしょうけどね・・・・
それが難しいんでしょうけどね・・・・
(キャリアブレイン 2012年10月17日 14:10 )
各種市場の総合マーケティングリサーチを行う富士経済は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の市場規模について、2020年には約9660億円まで拡大するとした調査報告をまとめた。11年(68億円)の140倍を超える規模拡大が見込まれることになる。また、福祉用具レンタルサービスなどの市場については、倍以上に拡大するとしている。
富士経済では、今年6月から8月にかけて、高齢者の生活を支援する製品や介護サービスの国内市場について調査。その結果を基に20年の市場規模などについて予測した。
その結果、サ高住の市場規模(事業売上額)は約9660億円、施設数は約1万7000件に達すると予測した。制度が始まった11年と比較すると、市場規模では142.1倍、施設数では151.8倍の拡大となる。急拡大するサ高住について富士経済では、「高齢者施設の代替としての役割も期待されるだけに、参入事業者にとっては、継続的な運営が可能なビジネスモデルの構築こそが重要ではないか」としている。
また、認知症の要介護者の動作をセンサーが感知して介護者などに知らせ、徘徊や転倒を防止できるようにする「徘徊・転倒防止機器」の市場規模(メーカー販売額)については、約53億円と予測。11年(約19億円)の2.8倍近くにまで拡大するとした。その背景について、富士経済では「病院だけでなく、サ高住や有料老人ホーム、あるいは在宅での需要が高まるため」と分析している。そのほか、福祉用具レンタルサービスの市場規模(事業売上額)についても、11年(約2240億円)の倍以上となる約5260億円まで拡大すると予測している。
【多●正芳、●は木へんに朶】

2012年10月20日
全国の包括の精鋭たちが缶詰に・・・
『全国の包括の精鋭たちが缶詰に――地域包括ケア推進指導者養成研修レポ』
(ケアマネジメントオンライン 2012/10/09 09:00 配信 )
厚生労働省は、10月3日・4日の2日間にわたり、平成24年度地域包括ケア推進指導者養成研修(中央研修)が開催された。
平成22年度から開催されている同研修は、地域包括支援センターにおけるさまざまな業務を円滑に進めることを目的に、センター長のマネジメントに関する講義や演習を行っている。3年目の今年で、全国のセンター長研修が終了することになる。
受講者は、地域包括支援センターの業務について幅広一件と経験を有する人で、かつ都道府県より受講推薦を受けた者、約100名。全国から選ばれた、いわば生え抜きの地域包括支援センター長たちである。
具体的な研修の目標は、新たに導入された地域包括ケアを推進するため、地域包括支援センターの管理者として求められる各種マネジメントや、地域において果たすべきセンターの役割を理解し、保険者と協働してセンターの方向性や目標を設定するなど、各地域においてリーダー的な役割を果たせる人材を養成することにある。
また、法改正を踏まえて、改めて位置づけられた地域ケア会議の意義や運営方法等についての理解を深めることにより、他職種協働による地域包括支援ネットワーク構築について管理者としての実践力を高めることにある。

3日は午後1時より5時半まで講義が、4日は午前9時半から午後4時20分まで講義と演習により、国が進めているシステムや今後のセンターの方向性がブレることなく、同じ方向を向けるようにすることが目的。今回は、その1日目の様子をレポートする。
1日目はオリエンテーションの後、最初に老健局総務課による「介護保険制度改正の概要及び地域包括ケアの理念」の講義が行われ、理念の再確認をしながら、今後どのように自治体と協働しながら、地域包括ケアを推進するかを考えるための基礎資料とした。
続いて行われた、同局老人保健課による「これからの介護予防~地域づくりによる介護予防の推進」の講義では、平成22年から実施されている新たな介護予防事業の取り組みについて、その成果や今後の課題などが示された。
この日最後の講義は、日本看護協会による「センター長のマネジメント能力の向上」。地域包括支援センターのセンター長として、各種マネジメント能力を向上させ、保険者とも協働しつつ、地域における今後のセンターの方向性や目標を設定する能力を養成する。
地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターでの仕事は、これまでの福祉や介護にありがちな観念論や感情論を極力廃し、わかりやすくシステム化されたルールに則って粛々と業務を行うことが求められる。そのためには事業計画や行動計画が必須で、それを実行に移すことがすなわちマネジメントであり、この講義では、職場に対するマネジメント、地域に対するマネジメント、目標を達成するためのマネジメント、政策に対するマネジメントなどが、事例とともに示された。
この中央研修を終了したものは、都道府県や市町村における研修の講師となり、講義の内容や制度の理念を実践の場で広げていく伝道師となる。
(ケアマネジメントオンライン 2012/10/09 09:00 配信 )
厚生労働省は、10月3日・4日の2日間にわたり、平成24年度地域包括ケア推進指導者養成研修(中央研修)が開催された。
平成22年度から開催されている同研修は、地域包括支援センターにおけるさまざまな業務を円滑に進めることを目的に、センター長のマネジメントに関する講義や演習を行っている。3年目の今年で、全国のセンター長研修が終了することになる。
受講者は、地域包括支援センターの業務について幅広一件と経験を有する人で、かつ都道府県より受講推薦を受けた者、約100名。全国から選ばれた、いわば生え抜きの地域包括支援センター長たちである。
具体的な研修の目標は、新たに導入された地域包括ケアを推進するため、地域包括支援センターの管理者として求められる各種マネジメントや、地域において果たすべきセンターの役割を理解し、保険者と協働してセンターの方向性や目標を設定するなど、各地域においてリーダー的な役割を果たせる人材を養成することにある。
また、法改正を踏まえて、改めて位置づけられた地域ケア会議の意義や運営方法等についての理解を深めることにより、他職種協働による地域包括支援ネットワーク構築について管理者としての実践力を高めることにある。

3日は午後1時より5時半まで講義が、4日は午前9時半から午後4時20分まで講義と演習により、国が進めているシステムや今後のセンターの方向性がブレることなく、同じ方向を向けるようにすることが目的。今回は、その1日目の様子をレポートする。
1日目はオリエンテーションの後、最初に老健局総務課による「介護保険制度改正の概要及び地域包括ケアの理念」の講義が行われ、理念の再確認をしながら、今後どのように自治体と協働しながら、地域包括ケアを推進するかを考えるための基礎資料とした。
続いて行われた、同局老人保健課による「これからの介護予防~地域づくりによる介護予防の推進」の講義では、平成22年から実施されている新たな介護予防事業の取り組みについて、その成果や今後の課題などが示された。
この日最後の講義は、日本看護協会による「センター長のマネジメント能力の向上」。地域包括支援センターのセンター長として、各種マネジメント能力を向上させ、保険者とも協働しつつ、地域における今後のセンターの方向性や目標を設定する能力を養成する。
地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターでの仕事は、これまでの福祉や介護にありがちな観念論や感情論を極力廃し、わかりやすくシステム化されたルールに則って粛々と業務を行うことが求められる。そのためには事業計画や行動計画が必須で、それを実行に移すことがすなわちマネジメントであり、この講義では、職場に対するマネジメント、地域に対するマネジメント、目標を達成するためのマネジメント、政策に対するマネジメントなどが、事例とともに示された。
この中央研修を終了したものは、都道府県や市町村における研修の講師となり、講義の内容や制度の理念を実践の場で広げていく伝道師となる。
2012年10月18日
日常的なリハビリを介護職に- リハビリの協働でシンポジウム
(キャリアブレイン 2012年10月05日 20:47 )
このほど開かれた「第23回全国介護老人保健施設大会」では、「必要とされるリハビリテーション」をテーマに、リハビリ専門職などの協働を考えるシンポジウムが行われた。老健には在宅復帰のための機能が求められているが、日常生活の中で行うリハビリを介護職が提供するという視点が示された。

「第23回全国介護老人保健施設大会」では、リハビリ専門職などの協同を考えるシンポジウムが行われた
介護老人保健施設せんだんの丘(仙台市)の土井勝幸施設長は、在宅復帰への取り組みについて報告した。
同施設では、これまで在宅復帰する利用者は少数だったが、3年ほど前に地域へ戻ってもらうためのプロジェクトを開始した。現在では在宅復帰率は60%で推移している。
土井氏は、入所時に利用者の家族に対して、生活機能を向上させ、地域に戻ってもらうための施設であることをしっかり説明することの重要性を指摘する。また、入所時のインテークを重視しており、自宅を訪問した時に把握した利用者のニーズが、施設内の介護力で本当に達成できるのか、確認する必要があると言う。
土井氏は在宅に復帰する上で、「頻回な訪問指導」「頻回なカンファレンス」「退所後の適切なフォロー体制」が重要なポイントだとする。
施設では、リハビリ専門職をはじめ、相談員、介護職員、看護職員も利用者の状況に応じて訪問させている。また、利用者の状況は刻々と変わるため、アセスメントに基づいて、適宜カンファレンスを行うという。
そして、退所前、退所後に自宅を訪問し、利用者の生活状況を見て、ショートステイの活用を提案している。機能が低下してしまった時には、再度入所してもらう。土井氏は、地域に戻れば、施設と在宅の「往復型」の支援に切り替わると言う。
土井氏は、地域でケアを継続していく上での主役はあくまで介護職だと指摘する。毎日の生活には、リハビリ専門職は配置できないが、これまでのリハビリを再現し、反復しながら、自立を支援する必要がある。そのためにも、日常生活のリハビリは、介護職に担ってもらう必要がある。
リハビリ専門職は、例えば、家の前の石畳を歩けるのかという課題が浮上すれば、介護職と一緒に訪問してアセスメントするほか、自宅の動線がふさがっているならば、環境を調整するといった役割が重要になるという。
■STによる日常生活場面での援助
日本言語聴覚士協会の深浦順一会長は、老健で言語聴覚士(ST)がかかわる障害として、摂食嚥下障害が増えているほか、認知機能の低下で、コミュニケーションに問題を生じている人が多いと指摘した。
高齢者における摂食・嚥下障害の要因として、▽加齢に伴う解剖学的、機能的低下▽意識レベル、認知レベルの低下▽脳血管障害に伴う知覚低下、運動低下-が見られるという。これらによって、特に「不顕性誤嚥」という“むせ”が生じない誤嚥のリスクが高まるという。
深浦氏は、誤嚥しないための方法として、活動性を高め、意識レベルを上げるほか、嚥下訓練を行ったり、多職種で共通認識を持って、摂食指導を行うことなどを挙げた。
また、誤嚥しても肺炎にならないためには、▽活動性を高める▽呼吸・発声機能を高める▽口腔・咽頭を清潔にする-などの方法を挙げた。
さらに深浦氏は、高齢者の状態を詳細に、総合的に把握しながら対応することが重要と指摘するほか、日常生活場面での援助において、STとしての専門性を発揮しながら、多職種と協働したいと訴えた。【大戸豊】
このほど開かれた「第23回全国介護老人保健施設大会」では、「必要とされるリハビリテーション」をテーマに、リハビリ専門職などの協働を考えるシンポジウムが行われた。老健には在宅復帰のための機能が求められているが、日常生活の中で行うリハビリを介護職が提供するという視点が示された。

「第23回全国介護老人保健施設大会」では、リハビリ専門職などの協同を考えるシンポジウムが行われた
介護老人保健施設せんだんの丘(仙台市)の土井勝幸施設長は、在宅復帰への取り組みについて報告した。
同施設では、これまで在宅復帰する利用者は少数だったが、3年ほど前に地域へ戻ってもらうためのプロジェクトを開始した。現在では在宅復帰率は60%で推移している。
土井氏は、入所時に利用者の家族に対して、生活機能を向上させ、地域に戻ってもらうための施設であることをしっかり説明することの重要性を指摘する。また、入所時のインテークを重視しており、自宅を訪問した時に把握した利用者のニーズが、施設内の介護力で本当に達成できるのか、確認する必要があると言う。
土井氏は在宅に復帰する上で、「頻回な訪問指導」「頻回なカンファレンス」「退所後の適切なフォロー体制」が重要なポイントだとする。
施設では、リハビリ専門職をはじめ、相談員、介護職員、看護職員も利用者の状況に応じて訪問させている。また、利用者の状況は刻々と変わるため、アセスメントに基づいて、適宜カンファレンスを行うという。
そして、退所前、退所後に自宅を訪問し、利用者の生活状況を見て、ショートステイの活用を提案している。機能が低下してしまった時には、再度入所してもらう。土井氏は、地域に戻れば、施設と在宅の「往復型」の支援に切り替わると言う。
土井氏は、地域でケアを継続していく上での主役はあくまで介護職だと指摘する。毎日の生活には、リハビリ専門職は配置できないが、これまでのリハビリを再現し、反復しながら、自立を支援する必要がある。そのためにも、日常生活のリハビリは、介護職に担ってもらう必要がある。
リハビリ専門職は、例えば、家の前の石畳を歩けるのかという課題が浮上すれば、介護職と一緒に訪問してアセスメントするほか、自宅の動線がふさがっているならば、環境を調整するといった役割が重要になるという。
■STによる日常生活場面での援助
日本言語聴覚士協会の深浦順一会長は、老健で言語聴覚士(ST)がかかわる障害として、摂食嚥下障害が増えているほか、認知機能の低下で、コミュニケーションに問題を生じている人が多いと指摘した。
高齢者における摂食・嚥下障害の要因として、▽加齢に伴う解剖学的、機能的低下▽意識レベル、認知レベルの低下▽脳血管障害に伴う知覚低下、運動低下-が見られるという。これらによって、特に「不顕性誤嚥」という“むせ”が生じない誤嚥のリスクが高まるという。
深浦氏は、誤嚥しないための方法として、活動性を高め、意識レベルを上げるほか、嚥下訓練を行ったり、多職種で共通認識を持って、摂食指導を行うことなどを挙げた。
また、誤嚥しても肺炎にならないためには、▽活動性を高める▽呼吸・発声機能を高める▽口腔・咽頭を清潔にする-などの方法を挙げた。
さらに深浦氏は、高齢者の状態を詳細に、総合的に把握しながら対応することが重要と指摘するほか、日常生活場面での援助において、STとしての専門性を発揮しながら、多職種と協働したいと訴えた。【大戸豊】
2012年10月17日
施設こそ24時間サービスに参入を・・・
「施設こそ24時間サービスに参入を」- 介護保険推進サミットの分科会
(キャリアブレイン 2012年10月05日 20:22 )
「第13回介護保険推進全国サミットinひがしおうみ」の分科会「定期巡回・随時対応サービス~訪問介護のパラダイム転換~」が4日、滋賀県東近江市で開かれた。参加したパネリストからは、今年4月から導入された定期訪問・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)について、24時間対応するためのノウハウと人材の蓄積がある特別養護老人ホーム(特養)などの施設こそ、このサービスに積極的に参入すべきとする意見が相次いだ。

分科会「定期巡回・随時対応サービス~訪問介護のパラダイム転換~」(4日、滋賀県東近江市内)
コーディネーターを務めた龍谷大名誉教授の池田省三氏は、現在の訪問介護は、受給者1人1日当たりの平均訪問回数が 0.6 回程度であるなどのデータを示した上で、「訪問介護だけでは、在宅の介護ニーズに十分対応できているとは言えない」と指摘。短時間の訪問を1日に何度も実施する24時間訪問サービスの普及の必要性を強く訴えた。一方、同サービスを普及させる上での課題として、▽介護業界に多い小規模事業所では、24時間365日のサービス提供を実現するのは困難▽特に、随時対応の依頼が相次いだ場合は、対応が難しいと考えられている▽サービスを提供するだけの人材確保ができない-などを提示した。
24時間訪問サービスを手がける小田原福祉会理事長の時田純氏は、特養などの介護施設では、24時間365日にわたってサービスを提供できるシステムと人材が既に整っていると指摘。一方、現在の訪問介護事業所では、そのためのノウハウや人材が十分に蓄積されていないとした上で、「特養が(24時間対応サービスに)積極的に乗り出すべき」と訴えた。他のパネリストも時田氏と同様の見解を述べた。
同じく24時間訪問サービスを手がけるジャパンケアグループ代表の対馬徳昭氏は、随時対応の依頼について、「利用者のアセスメントを十分に行い、適切なケアプランを立てれば、随時対応の依頼はそれほど多くない」と指摘。さらに、窓口となるオペレーターが電話だけで対応できる場合も多く、実際に依頼に応じて介護職員や看護職員の派遣するのは「依頼の半分程度」とも述べた。
また、東大高齢社会総合研究機構特任教授の辻哲夫氏は、在宅医療を含めた地域包括ケアの実現に向け、千葉県柏市で進めている実証研究事業「柏プロジェクト」について説明。急速に高齢化が進む都市部にも対応できる地域包括ケアシステムの具現化を目指し、2014年1月には、柏市豊四季台地区に、在宅療養支援診療所や地域包括支援センター、24時間訪問サービスの事業所などを含めたサービス付き高齢者向け住宅を整備する方針であることも紹介した。
(キャリアブレイン 2012年10月05日 20:22 )
「第13回介護保険推進全国サミットinひがしおうみ」の分科会「定期巡回・随時対応サービス~訪問介護のパラダイム転換~」が4日、滋賀県東近江市で開かれた。参加したパネリストからは、今年4月から導入された定期訪問・随時対応型訪問介護看護(24時間訪問サービス)について、24時間対応するためのノウハウと人材の蓄積がある特別養護老人ホーム(特養)などの施設こそ、このサービスに積極的に参入すべきとする意見が相次いだ。

分科会「定期巡回・随時対応サービス~訪問介護のパラダイム転換~」(4日、滋賀県東近江市内)
コーディネーターを務めた龍谷大名誉教授の池田省三氏は、現在の訪問介護は、受給者1人1日当たりの平均訪問回数が 0.6 回程度であるなどのデータを示した上で、「訪問介護だけでは、在宅の介護ニーズに十分対応できているとは言えない」と指摘。短時間の訪問を1日に何度も実施する24時間訪問サービスの普及の必要性を強く訴えた。一方、同サービスを普及させる上での課題として、▽介護業界に多い小規模事業所では、24時間365日のサービス提供を実現するのは困難▽特に、随時対応の依頼が相次いだ場合は、対応が難しいと考えられている▽サービスを提供するだけの人材確保ができない-などを提示した。
24時間訪問サービスを手がける小田原福祉会理事長の時田純氏は、特養などの介護施設では、24時間365日にわたってサービスを提供できるシステムと人材が既に整っていると指摘。一方、現在の訪問介護事業所では、そのためのノウハウや人材が十分に蓄積されていないとした上で、「特養が(24時間対応サービスに)積極的に乗り出すべき」と訴えた。他のパネリストも時田氏と同様の見解を述べた。
同じく24時間訪問サービスを手がけるジャパンケアグループ代表の対馬徳昭氏は、随時対応の依頼について、「利用者のアセスメントを十分に行い、適切なケアプランを立てれば、随時対応の依頼はそれほど多くない」と指摘。さらに、窓口となるオペレーターが電話だけで対応できる場合も多く、実際に依頼に応じて介護職員や看護職員の派遣するのは「依頼の半分程度」とも述べた。
また、東大高齢社会総合研究機構特任教授の辻哲夫氏は、在宅医療を含めた地域包括ケアの実現に向け、千葉県柏市で進めている実証研究事業「柏プロジェクト」について説明。急速に高齢化が進む都市部にも対応できる地域包括ケアシステムの具現化を目指し、2014年1月には、柏市豊四季台地区に、在宅療養支援診療所や地域包括支援センター、24時間訪問サービスの事業所などを含めたサービス付き高齢者向け住宅を整備する方針であることも紹介した。
2012年10月15日
超高齢社会到来、まずは10年後に備えて・・・
『超高齢社会到来、まずは10年後に備えて- 医療経済研究機構がシンポ 』
(キャリアブレイン 2012年09月28日 20:49)
2050年には、人口の4割近くが65歳以上になる-。未曽有の「超高齢社会」に備えるため、医療経済研究機構は28日、「超高齢社会と医療保障のあり方」をテーマにシンポジウムを開催した。この中で基調講演した国立社会保障・人口問題研究所の西村周三所長は、50年後に備える視点を忘れないことが大事と強調した上で、ひとまずは、ある程度の予測が可能な10年後に備えるよう呼び掛けた。

国立社会保障・人口問題研究所の西村周三所長(28日、東京都内)
西村所長は、元気な65―74歳を、支えられる側の高齢者として考えるかどうかや、医療機関を利用する頻度が高いとされる単独世帯の増加にどう対応するかを、これからの高齢社会を考える上でのキーワードとして提示。また、10年と25年の75歳以上の人口を比べると、東京都や神奈川県などで大幅に増える一方、鳥取県や島根県では、ほぼ変わらないとの統計を示し、地域によって高齢化の進み方に差があることも考慮すべきだと指摘した。
パネルディスカッションでは、日本慢性期医療協会の武久洋三会長が、患者の高齢化に対応するためには、多臓器の疾患を診ることができる「高齢者総合医」を養成したり、「認知症科」の標榜を認めて、認知症患者が、受診する医療機関で迷わないようにしたりする必要があるとの考えを示した。
また、都内で在宅医療に従事する医療法人社団三育会の英裕雄理事長は、患者が在宅で最期を迎えるには、患者自身が元気な時に、健康状態を相談できる医師を確保したり、どこで最期を迎えたいかをイメージしたりしておくことが重要だと指摘した。【佐藤貴彦】
(キャリアブレイン 2012年09月28日 20:49)
2050年には、人口の4割近くが65歳以上になる-。未曽有の「超高齢社会」に備えるため、医療経済研究機構は28日、「超高齢社会と医療保障のあり方」をテーマにシンポジウムを開催した。この中で基調講演した国立社会保障・人口問題研究所の西村周三所長は、50年後に備える視点を忘れないことが大事と強調した上で、ひとまずは、ある程度の予測が可能な10年後に備えるよう呼び掛けた。

国立社会保障・人口問題研究所の西村周三所長(28日、東京都内)
西村所長は、元気な65―74歳を、支えられる側の高齢者として考えるかどうかや、医療機関を利用する頻度が高いとされる単独世帯の増加にどう対応するかを、これからの高齢社会を考える上でのキーワードとして提示。また、10年と25年の75歳以上の人口を比べると、東京都や神奈川県などで大幅に増える一方、鳥取県や島根県では、ほぼ変わらないとの統計を示し、地域によって高齢化の進み方に差があることも考慮すべきだと指摘した。
パネルディスカッションでは、日本慢性期医療協会の武久洋三会長が、患者の高齢化に対応するためには、多臓器の疾患を診ることができる「高齢者総合医」を養成したり、「認知症科」の標榜を認めて、認知症患者が、受診する医療機関で迷わないようにしたりする必要があるとの考えを示した。
また、都内で在宅医療に従事する医療法人社団三育会の英裕雄理事長は、患者が在宅で最期を迎えるには、患者自身が元気な時に、健康状態を相談できる医師を確保したり、どこで最期を迎えたいかをイメージしたりしておくことが重要だと指摘した。【佐藤貴彦】
2012年10月06日
理想と思われる介護に世代間の格差あり・・・
『理想と思われる介護に世代間の格差あり――社会保障を支える世代に関する意識調査』
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/21 09:00 配信)
厚生労働省は、8月30日、「平成22年社会保障を支える世代に関する意識等調査」の結果を発表した。
同調査は、社会保障を支える世代の就業状況や子育て、親への支援の状況の実態を把握するとともに、理想の働き方や社会保障に係わる負担のあり方についての意識を調査し、政策の基礎資料とすることを目的にしている。対象は20歳以上65歳未満の世帯員で、7,973人中、7,413人から回答が寄せられている。
そのうち、介護について、「両親に対して手助けや見守りをしている」場合の詳細結果を紹介する。
【両親の手助けや見守りの状況】⇒実施している半数以上は、要支援・要介護の場合
現在、両親に対して手助けや見守りをしているか否かを聞いたところ、どの年代でも「していない」が最も多く、50歳以上では「母親のみしている」が11.9%となっている。

(クリックして拡大)
「手助けや見守りをしている」人の要介護度の内訳では、半数以上が要支援、要介護に該当し、そのうち、最も多いのが要支援2で、父親17.3%、母親15.1%だった。残りは二次予防の対象者が1.6%、非該当が約30%、不明が約10%となっている。
【利用した介護等サービス】⇒通所介護が最多
手助けや見守りをしている両親が、二次予防の対象者か、要支援、要介護である場合、これまで利用したサービスは、「通所介護」41.2%で最も多く、次いで「訪問介護」26%、「通所リハビリテーション」14.8%となっている。
【手助けや見守りを行うに当たり負担と感じること】⇒「ストレスや精神的負担が大きい」
両親の手助けや見守りをしていると答えた人に介護への負担を聞いたところ、男女とも年齢が上がるにつれて「ストレスや精神的負担が大きい」と答えている。
【理想と思われる親への介護】⇒世代間で格差
理想と思われる介護については、20歳代、30歳代では「子どもが親の世話をする」が、40歳代、50~64歳では「自宅でホームヘルパー等を利用して世話をする」が最も多くなっていて、世代間に格差が見られた。
【両親との経済的な支援関係】⇒親への仕送りは「必要としていない」が最多
両親との経済的な支援関係については、どの年齢階層においても、「あなた、または、あなたの配偶者の親の間に仕送りはない」が最も多くなっている。その理由については、どの年齢階級においても「仕送りを必要としていない、または、必要とされていない」が最も多かった。
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/21 09:00 配信)
厚生労働省は、8月30日、「平成22年社会保障を支える世代に関する意識等調査」の結果を発表した。
同調査は、社会保障を支える世代の就業状況や子育て、親への支援の状況の実態を把握するとともに、理想の働き方や社会保障に係わる負担のあり方についての意識を調査し、政策の基礎資料とすることを目的にしている。対象は20歳以上65歳未満の世帯員で、7,973人中、7,413人から回答が寄せられている。
そのうち、介護について、「両親に対して手助けや見守りをしている」場合の詳細結果を紹介する。
【両親の手助けや見守りの状況】⇒実施している半数以上は、要支援・要介護の場合
現在、両親に対して手助けや見守りをしているか否かを聞いたところ、どの年代でも「していない」が最も多く、50歳以上では「母親のみしている」が11.9%となっている。

(クリックして拡大)
「手助けや見守りをしている」人の要介護度の内訳では、半数以上が要支援、要介護に該当し、そのうち、最も多いのが要支援2で、父親17.3%、母親15.1%だった。残りは二次予防の対象者が1.6%、非該当が約30%、不明が約10%となっている。
【利用した介護等サービス】⇒通所介護が最多
手助けや見守りをしている両親が、二次予防の対象者か、要支援、要介護である場合、これまで利用したサービスは、「通所介護」41.2%で最も多く、次いで「訪問介護」26%、「通所リハビリテーション」14.8%となっている。
【手助けや見守りを行うに当たり負担と感じること】⇒「ストレスや精神的負担が大きい」
両親の手助けや見守りをしていると答えた人に介護への負担を聞いたところ、男女とも年齢が上がるにつれて「ストレスや精神的負担が大きい」と答えている。
【理想と思われる親への介護】⇒世代間で格差
理想と思われる介護については、20歳代、30歳代では「子どもが親の世話をする」が、40歳代、50~64歳では「自宅でホームヘルパー等を利用して世話をする」が最も多くなっていて、世代間に格差が見られた。
【両親との経済的な支援関係】⇒親への仕送りは「必要としていない」が最多
両親との経済的な支援関係については、どの年齢階層においても、「あなた、または、あなたの配偶者の親の間に仕送りはない」が最も多くなっている。その理由については、どの年齢階級においても「仕送りを必要としていない、または、必要とされていない」が最も多かった。
2012年10月03日
オランダではケアマネジメントとケア提供を一貫して・・・
オランダではケアマネジメントとケア提供を一貫して担う在宅ケア事業者が急成長―研究会レポ(2)
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/13 12:00 配信)
8月28日、東京・赤坂でシルバーサービス振興会の月例研究会が開催された。労働政策研究・研修機構研究員の堀田聰子氏による、「オランダの地域包括ケアとコミュニティケアの担い手たち」と題した講演の後半、統合ケアの観点から見たオランダのケア提供体制について報告する。
統合ケアは、90年代の欧米でのヘルスケア政策改革に共通する概念。複数の慢性疾患を抱えて地域で暮らす人が増え、長期ケアに関わるサービスの断片化と連続性の欠如が問題になっていた。さらに、障害者や慢性疾患患者に対する医療に対する考え方が「治す医療」から「支える医療」に変わってきたことなどから、諸外国では統合ケアへの流れが進んでいったと堀田氏はいう。
統合ケアの概念や要素は国によってさまざまだが、ここでは運営の統合、サービスの共同配置、ケアのネットワーク、ケースマネジメント、切れ目ないケア提供に向けた連携、サービス付き住宅の6つの観点からオランダのケア提供体制が紹介された。
オランダでは80年代以降、プライマリケアの一体性を高める観点から、多職種協働のプライマリケアセンター整備が推進された。90年代には地域看護とホームケア、助産ケアの組織が統合され、在宅ケアが一つのドメインに。
プライマリケアセンターには、家庭医、在宅ケア、ソーシャルワーカーを三本柱としてリハビリ、栄養士、小児ケア、薬局等を配置。福祉機能も集約され、高齢者に対しては日本のソーシャルワーカー的な存在である高齢者アドバイザーが、住宅や介護、福祉等に関わる助言や必要な支援をアレンジする場合もある。ケースマネジメントの制度上の位置づけはないため、そのあり方は多様で、高齢者アドバイザーのほか家庭医、看護師、介護士など、様々な職種が担っている。また、ケースマネジメントとケアを一体的に提供する組織も少なくないと堀田氏はいう。

中でも、急成長しているのが、地域看護師が起業した在宅ケアの事業者だ。1チーム最大12人のナースが約40~60人の利用者を担当し、全土で約5000人のナースが総計約5万人の利用者を支援している。各チームに事務職はおらず、わずか30人の管理部門が業務管理を担当。他の事業者が平均25%かけている間接費を8%に抑えている。ナースは6割以上が学士レベル以上の地域看護師で、あらゆるタイプの利用者に対してケースマネジメントから包括的なケア提供まで、全プロセスを担う。クライアント1人あたりのコストは他の在宅ケア組織の半分でありながら、利用者満足度は1位、従業員満足度も高く、全産業を合わせて最も成長している事業者だと堀田氏はいう。
この事業者のコストダウンのポイントとしては、セルフケアやインフォーマルサービスを引き出して専門職ケアを次第に置き換えていること、分業せず1人がトータルにケアする体制をとり、移動や連絡・調整の無駄を省いていること、ヒエラルキーのないフラットな組織にしてナースがクライアントとの関係構築に集中できる環境を作り、効率性を高めていること等を、堀田氏は挙げている。
オランダではまた、2000年代に入ってからコーディネイトされた認知症ケアの実現に向けた取り組みが進められたという。全国57地域において、認知症の人と介護者の視点から地域ごとの課題を抽出。当事者の言葉を用いて整理された14の問題領域に対応して認知症の人と介護者、専門職が改善に向けたプロジェクトを実施。これにより、各地域におけるよい認知症ケアを明確化。どの段階で誰が関わるのかといったガイドラインが作られ、各地域でガイドラインに沿ったケア購入に向けた実験を経て、全土にケースマネジメントを含むコーディネートされた認知症ケアが普及した。
堀田氏はこのほか、オランダでは産業界と教育界が対話を繰り返して、資格のあり方の検討や教育カリキュラムの改訂を繰り返していることなどについても紹介。日本でも、ケア関連領域横断のプラットフォームを設置し、実践と理論を併せて長期的展望を描いた上での現状の評価と、ケア関連資格のあり方を実践から振り返る視点を加えて定期的に見直していくことの必要性を訴えた。
◎シルバーサービス振興会
(ケアマネジメントオンライン 2012/09/13 12:00 配信)
8月28日、東京・赤坂でシルバーサービス振興会の月例研究会が開催された。労働政策研究・研修機構研究員の堀田聰子氏による、「オランダの地域包括ケアとコミュニティケアの担い手たち」と題した講演の後半、統合ケアの観点から見たオランダのケア提供体制について報告する。
統合ケアは、90年代の欧米でのヘルスケア政策改革に共通する概念。複数の慢性疾患を抱えて地域で暮らす人が増え、長期ケアに関わるサービスの断片化と連続性の欠如が問題になっていた。さらに、障害者や慢性疾患患者に対する医療に対する考え方が「治す医療」から「支える医療」に変わってきたことなどから、諸外国では統合ケアへの流れが進んでいったと堀田氏はいう。
統合ケアの概念や要素は国によってさまざまだが、ここでは運営の統合、サービスの共同配置、ケアのネットワーク、ケースマネジメント、切れ目ないケア提供に向けた連携、サービス付き住宅の6つの観点からオランダのケア提供体制が紹介された。
オランダでは80年代以降、プライマリケアの一体性を高める観点から、多職種協働のプライマリケアセンター整備が推進された。90年代には地域看護とホームケア、助産ケアの組織が統合され、在宅ケアが一つのドメインに。
プライマリケアセンターには、家庭医、在宅ケア、ソーシャルワーカーを三本柱としてリハビリ、栄養士、小児ケア、薬局等を配置。福祉機能も集約され、高齢者に対しては日本のソーシャルワーカー的な存在である高齢者アドバイザーが、住宅や介護、福祉等に関わる助言や必要な支援をアレンジする場合もある。ケースマネジメントの制度上の位置づけはないため、そのあり方は多様で、高齢者アドバイザーのほか家庭医、看護師、介護士など、様々な職種が担っている。また、ケースマネジメントとケアを一体的に提供する組織も少なくないと堀田氏はいう。

中でも、急成長しているのが、地域看護師が起業した在宅ケアの事業者だ。1チーム最大12人のナースが約40~60人の利用者を担当し、全土で約5000人のナースが総計約5万人の利用者を支援している。各チームに事務職はおらず、わずか30人の管理部門が業務管理を担当。他の事業者が平均25%かけている間接費を8%に抑えている。ナースは6割以上が学士レベル以上の地域看護師で、あらゆるタイプの利用者に対してケースマネジメントから包括的なケア提供まで、全プロセスを担う。クライアント1人あたりのコストは他の在宅ケア組織の半分でありながら、利用者満足度は1位、従業員満足度も高く、全産業を合わせて最も成長している事業者だと堀田氏はいう。
この事業者のコストダウンのポイントとしては、セルフケアやインフォーマルサービスを引き出して専門職ケアを次第に置き換えていること、分業せず1人がトータルにケアする体制をとり、移動や連絡・調整の無駄を省いていること、ヒエラルキーのないフラットな組織にしてナースがクライアントとの関係構築に集中できる環境を作り、効率性を高めていること等を、堀田氏は挙げている。
オランダではまた、2000年代に入ってからコーディネイトされた認知症ケアの実現に向けた取り組みが進められたという。全国57地域において、認知症の人と介護者の視点から地域ごとの課題を抽出。当事者の言葉を用いて整理された14の問題領域に対応して認知症の人と介護者、専門職が改善に向けたプロジェクトを実施。これにより、各地域におけるよい認知症ケアを明確化。どの段階で誰が関わるのかといったガイドラインが作られ、各地域でガイドラインに沿ったケア購入に向けた実験を経て、全土にケースマネジメントを含むコーディネートされた認知症ケアが普及した。
堀田氏はこのほか、オランダでは産業界と教育界が対話を繰り返して、資格のあり方の検討や教育カリキュラムの改訂を繰り返していることなどについても紹介。日本でも、ケア関連領域横断のプラットフォームを設置し、実践と理論を併せて長期的展望を描いた上での現状の評価と、ケア関連資格のあり方を実践から振り返る視点を加えて定期的に見直していくことの必要性を訴えた。
◎シルバーサービス振興会