2012年07月12日
BPSDをもっとも起こしやすい認知症・・・
『BPSDをもっとも起こしやすい認知症――レビー小体型認知症講演会レポ(1)』
(ケアマネジメントオンライン 2012/07/05 09:00 配信)
6月25日(月)、紀伊國屋サザンシアターにて、精神科医の小阪憲司氏による講演会「発見者が語る――レビー小体型認知症を知っていますか?」が開催された。
小阪憲司氏は、聖マリアンナ医学研究所所長などを経て、現在はメディカルコートクリニック院長、横浜市立大学名誉教授。レビー小体型認知症の発見者として世界的に知られる。今回の講演は、5月に刊行された新著『第二の認知症――増えるレビー小体型認知症の今』刊行を記念してのもの。
日本のレビー小体認知症の患者は約64万人で、認知症全体の20%を占める。書名の「第二の認知症」は、アルツハイマー型認知症に次いで多い認知症という意味。講演は、近年、注目を集めているこの「第二の認知症」の第一人者が、症状の特徴や診断・治療例について語るのを直接聞く貴重な機会となった。
登壇した小阪氏は、まず、新著について、担当編集者の親族がレビー小体型認知症になり、「この病気についての本がなぜないのだろう」と思ったことが発刊のそもそものきっかけだったことに触れ、著書は発売1か月で増刷となり、「レビー小体型認知症への関心が高いことが改めて明らかになった」と語った。
レビー小体型認知症は、レビー小体により脳の神経細胞や全身の交感神経が障害され、幻視やパーキンソン病症状、認知障害を起こす病気。70歳前後で発病することが多く、男性患者が多いという。
「αシヌクレイン」といわれるタンパク質を主成分とするレビー小体は、1912年にドイツで、パーキンソン病の人の脳幹に存在することが発見された。以来、レビー小体は脳幹に現れても、大脳皮質には現われないというのが定説だったが、1976年に小阪氏が認知症とパーキンソンの症状を示す患者の大脳皮質にレビー小体を発見、世界で最初のレビー小体型認知症の症例報告となった。1980年代半ばから欧米でも同様の症例報告がなされ、1996年に診断基準ができ、レビー小体型認知症という病名が決まった。
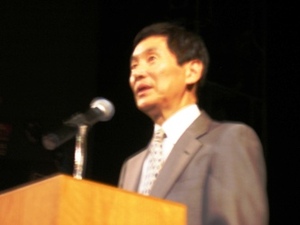
小阪氏は、レビー小体型認知症の特徴として下記のことをあげた。
・特徴的な症状として、幻視がある。
・筋肉が固くなり、転びやすいなどパーキンソン病の症状がある。
・大きな寝言などレム睡眠障害がある
・初期症状としてBPSDが見られ、ケアが大変。認知症の症状は遅れて出てくる。
・薬に過敏性があり、薬の使い方がむずかしい。
レビー小体認知症の症状である幻視は、「虫が這いまわる」「子どもたちが遊んでいる」など、実際には存在しないものが、「ありありと」見えるのが特徴だそう。
こうした症状に、精神科の医師は抗精神病薬を使用しがちだが、「それが症状を悪化させる原因に。レビー小体外型認知症に抗精神薬を使う場合は、ごく少量を使うことが大切です」。
また、認知症であっても脳の萎縮が目立たたないため、「年齢相応の変化」と言われてしまうことも。老年期うつ病やパーキンソン病と間違われることも多いそう。
レビー小体型認知症は、BPSD(周辺症状)が早期に出やすいのも大きな特徴。また、アルツハイマー型認知症の場合、ものがなくなると、「自分はしまったはずないのにないのは、身近な人が盗ったからだ」という記憶障害にもとづいたBPSDが多いのに対し、レビー小体型認知症は、「良い妻と悪い妻の2人がいる」など幻視に基づいた妄想で、かなり違いが。
「もっともBPSDを起こしやすい認知症ですから、本人も苦しめ、家族も苦しめます。この病気について知り、できるだけ早く診断して治療することが大切です」
◎紀伊國屋書店
(ケアマネジメントオンライン 2012/07/05 09:00 配信)
6月25日(月)、紀伊國屋サザンシアターにて、精神科医の小阪憲司氏による講演会「発見者が語る――レビー小体型認知症を知っていますか?」が開催された。
小阪憲司氏は、聖マリアンナ医学研究所所長などを経て、現在はメディカルコートクリニック院長、横浜市立大学名誉教授。レビー小体型認知症の発見者として世界的に知られる。今回の講演は、5月に刊行された新著『第二の認知症――増えるレビー小体型認知症の今』刊行を記念してのもの。
日本のレビー小体認知症の患者は約64万人で、認知症全体の20%を占める。書名の「第二の認知症」は、アルツハイマー型認知症に次いで多い認知症という意味。講演は、近年、注目を集めているこの「第二の認知症」の第一人者が、症状の特徴や診断・治療例について語るのを直接聞く貴重な機会となった。
登壇した小阪氏は、まず、新著について、担当編集者の親族がレビー小体型認知症になり、「この病気についての本がなぜないのだろう」と思ったことが発刊のそもそものきっかけだったことに触れ、著書は発売1か月で増刷となり、「レビー小体型認知症への関心が高いことが改めて明らかになった」と語った。
レビー小体型認知症は、レビー小体により脳の神経細胞や全身の交感神経が障害され、幻視やパーキンソン病症状、認知障害を起こす病気。70歳前後で発病することが多く、男性患者が多いという。
「αシヌクレイン」といわれるタンパク質を主成分とするレビー小体は、1912年にドイツで、パーキンソン病の人の脳幹に存在することが発見された。以来、レビー小体は脳幹に現れても、大脳皮質には現われないというのが定説だったが、1976年に小阪氏が認知症とパーキンソンの症状を示す患者の大脳皮質にレビー小体を発見、世界で最初のレビー小体型認知症の症例報告となった。1980年代半ばから欧米でも同様の症例報告がなされ、1996年に診断基準ができ、レビー小体型認知症という病名が決まった。
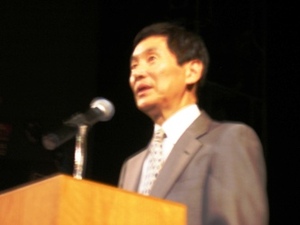
小阪氏は、レビー小体型認知症の特徴として下記のことをあげた。
・特徴的な症状として、幻視がある。
・筋肉が固くなり、転びやすいなどパーキンソン病の症状がある。
・大きな寝言などレム睡眠障害がある
・初期症状としてBPSDが見られ、ケアが大変。認知症の症状は遅れて出てくる。
・薬に過敏性があり、薬の使い方がむずかしい。
レビー小体認知症の症状である幻視は、「虫が這いまわる」「子どもたちが遊んでいる」など、実際には存在しないものが、「ありありと」見えるのが特徴だそう。
こうした症状に、精神科の医師は抗精神病薬を使用しがちだが、「それが症状を悪化させる原因に。レビー小体外型認知症に抗精神薬を使う場合は、ごく少量を使うことが大切です」。
また、認知症であっても脳の萎縮が目立たたないため、「年齢相応の変化」と言われてしまうことも。老年期うつ病やパーキンソン病と間違われることも多いそう。
レビー小体型認知症は、BPSD(周辺症状)が早期に出やすいのも大きな特徴。また、アルツハイマー型認知症の場合、ものがなくなると、「自分はしまったはずないのにないのは、身近な人が盗ったからだ」という記憶障害にもとづいたBPSDが多いのに対し、レビー小体型認知症は、「良い妻と悪い妻の2人がいる」など幻視に基づいた妄想で、かなり違いが。
「もっともBPSDを起こしやすい認知症ですから、本人も苦しめ、家族も苦しめます。この病気について知り、できるだけ早く診断して治療することが大切です」
◎紀伊國屋書店




