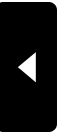2012年06月05日
一週間のご無沙汰でした!!
こんにちは(^_-) ふくえん熊本 平田です
昨日の一面では”野田再内閣改造”の事で・・あ~~でもない?こ~~でもない?の
議論がなされてたようですが・・・って、前に進むにはそこで立ち止まってる場合ではないように
思うのですが・・・!!
いきなり政治の話かよ~~って言われそう
難しい話??はこれぐらいにして(どこが・・って突っ込まれそう・・)(^_^;)
先週は甲佐まで行ったので、用事を済ませた後 ちょっと足を延ばし隣の美里町に
行って来ました


日本一の石段(3,333段)がある事で有名な所です。
その昔、「日本で最も長い階段」は山形県の出羽三山、羽黒山神社の参道杉並木でした。
登山口から山頂までの1700m、全2446段の階段です。
その後、日本中がバブルで騒がしくなると、熊本に3333段という階段ができました。
1988年3月に完成した釈迦院(金海山大恩教寺)の大石段です。全長1900m。
この釈迦院というのは別にバブル宗教施設というわけではなく、今から1200年以上前の
799年に開山した名門中の名門なんです。
私も一度トライしてみなくては・・・と思ってはいますが
次に旧砥用町にある所でちょっとした事で有名な橋みたいですが**
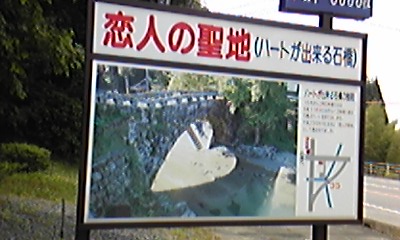
以前、”若っとランド”の番組で紹介されてました(*^_^*)
時間によって出来る「ハート型」!!私もテレビで知り、いつかは行ってみたいと思ってます

昨日の一面では”野田再内閣改造”の事で・・あ~~でもない?こ~~でもない?の
議論がなされてたようですが・・・って、前に進むにはそこで立ち止まってる場合ではないように
思うのですが・・・!!
いきなり政治の話かよ~~って言われそう

難しい話??はこれぐらいにして(どこが・・って突っ込まれそう・・)(^_^;)
先週は甲佐まで行ったので、用事を済ませた後 ちょっと足を延ばし隣の美里町に
行って来ました



日本一の石段(3,333段)がある事で有名な所です。
その昔、「日本で最も長い階段」は山形県の出羽三山、羽黒山神社の参道杉並木でした。
登山口から山頂までの1700m、全2446段の階段です。
その後、日本中がバブルで騒がしくなると、熊本に3333段という階段ができました。
1988年3月に完成した釈迦院(金海山大恩教寺)の大石段です。全長1900m。
この釈迦院というのは別にバブル宗教施設というわけではなく、今から1200年以上前の
799年に開山した名門中の名門なんです。
私も一度トライしてみなくては・・・と思ってはいますが

次に旧砥用町にある所でちょっとした事で有名な橋みたいですが**
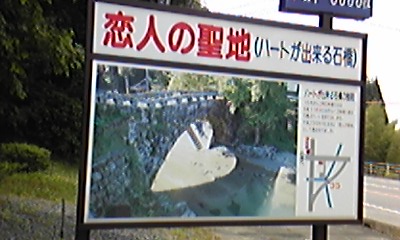
以前、”若っとランド”の番組で紹介されてました(*^_^*)
時間によって出来る「ハート型」!!私もテレビで知り、いつかは行ってみたいと思ってます

2012年06月02日
ケアマネージャーをネット検索・・・
『ケアマネージャーをネット検索 つくばのベンチャーがサービス開始』
利用者が自由に選択

【写真説明】「myケアマネ」の公式サイト。利用者がケアマネを比較して選べる
産業技術総合研究所の技術移転ベンチャーで福祉ロボット開発のライフロボティクス(つくば市梅園)は、介護サービスの利用者がインターネットの検索で、ケアマネージャーを自由に選べるシステムを開発した。判断に迷うケアマネ選びや、契約後にケアマネを交替させにくい現状を変え、利用者目線に立った介護サービスを構築するのが目的。同社は、システムを全国で使えるように展開し、普及させたい考えだ。
検索サービスは「my(マイ)ケアマネ」の名称で4月下旬に始まった。
利用方法は、介護サービスの利用者が無料で会員登録し、サイト画面上で居住地域を入力、登録事業所やケアマネを検索する。利用者が専門の「マイページ」を通じて、ケアマネに介護利用の困り事相談や、ケアマネのより詳しい情報が入手できる。電話でも相談を受け付け、事前に5人まで相談でき、ケアマネを選ぶことができる。
契約に至れば、利用者には同社から介護応援金(商品券5000円分)も贈られる。
これまで、介護サービスの利用者は、介護事業所からケアマネを紹介されて契約するが、自ら選択する自由度が低く、不満が残る場合があるという。
一生涯付き合う可能性もあるため、ケアマネの専門知識や性格を事前に知ることで、介護サービスの満足度を高めるのも、狙いの一つ。
同社は「ケアマネをどう選んだらいいか分からない利用者が多く、複数のケアマネを比較・検討できることで、相談しやすく頼りになる人を探せる。ケアマネにとっても競争原理が働き、資質向上につながるのでは」(尹祐根取締役)と長所を強調。
同社は契約に至った際にケアマネから手数料を得るほか、サイトへの広告収入を得てサービスを運営する。
今後は全国3万3千カ所の介護事業所を掲載し、地域のケアマネを選べるようにする。利用を増やすため、自治体の介護保険担当者らへの説明を進めていく方針だ。
(茨城新聞)2012年5月30日(水)
なんでも検索できる時代ですね・・・・
その内、福祉用具業者もネット検索される時代が来るのでしょうか(^_^;)
それでは
利用者が自由に選択

【写真説明】「myケアマネ」の公式サイト。利用者がケアマネを比較して選べる
産業技術総合研究所の技術移転ベンチャーで福祉ロボット開発のライフロボティクス(つくば市梅園)は、介護サービスの利用者がインターネットの検索で、ケアマネージャーを自由に選べるシステムを開発した。判断に迷うケアマネ選びや、契約後にケアマネを交替させにくい現状を変え、利用者目線に立った介護サービスを構築するのが目的。同社は、システムを全国で使えるように展開し、普及させたい考えだ。
検索サービスは「my(マイ)ケアマネ」の名称で4月下旬に始まった。
利用方法は、介護サービスの利用者が無料で会員登録し、サイト画面上で居住地域を入力、登録事業所やケアマネを検索する。利用者が専門の「マイページ」を通じて、ケアマネに介護利用の困り事相談や、ケアマネのより詳しい情報が入手できる。電話でも相談を受け付け、事前に5人まで相談でき、ケアマネを選ぶことができる。
契約に至れば、利用者には同社から介護応援金(商品券5000円分)も贈られる。
これまで、介護サービスの利用者は、介護事業所からケアマネを紹介されて契約するが、自ら選択する自由度が低く、不満が残る場合があるという。
一生涯付き合う可能性もあるため、ケアマネの専門知識や性格を事前に知ることで、介護サービスの満足度を高めるのも、狙いの一つ。
同社は「ケアマネをどう選んだらいいか分からない利用者が多く、複数のケアマネを比較・検討できることで、相談しやすく頼りになる人を探せる。ケアマネにとっても競争原理が働き、資質向上につながるのでは」(尹祐根取締役)と長所を強調。
同社は契約に至った際にケアマネから手数料を得るほか、サイトへの広告収入を得てサービスを運営する。
今後は全国3万3千カ所の介護事業所を掲載し、地域のケアマネを選べるようにする。利用を増やすため、自治体の介護保険担当者らへの説明を進めていく方針だ。
(茨城新聞)2012年5月30日(水)
なんでも検索できる時代ですね・・・・
その内、福祉用具業者もネット検索される時代が来るのでしょうか(^_^;)
それでは

2012年06月01日
サービスありきでアセスメントしていない?・・・
『サービスありきでアセスメントしていない?――認定ケアマネの会研修レポ(2)』
(ケアマネジメントオンライン 2012/05/23 12:00 配信)
5月12日に開催されたケアマネジメントキャリアアップ研修「ケアマネジメントとは何か」。ここでは研修の後半に行われた、5、6人ずつでのグループワークの様子を紹介する。
この研修の到達目標は、ケアマネジメント実践上の課題を明らかにすること。的確なアセスメント力を身につけるには、事例検討会で事例を深め、展開していく力を養うことが役に立つ。グループワークは、事例を深める上で自分に足りないアセスメントの視点、分析力に、他者との対比の中で気づくことを目的に行われた。
まず事例提供者から、模擬事例のプレゼンが行われた。時間は10分。「事例検討では検討課題を明確化し、10分で要点をまとめてプレゼンする力が求められる」と白木氏。聞く側は頭の中で情報を整理し、何を質問すればこの事例がわかるかを考えながら聞くことが大切。そして、スーパーバイザー(以下、SVor)は情報を板書し、図式化していくことで、同席者が情報を共有しやすくする。出席者全員で板書の情報を共有すること、つまり配布された事例の資料に個々で情報を書き込むのではなく、全員が顔を上げて事例提供者のプレゼンを聞けるようにすることも重要だという。
研修では、このあと事例を深める質問を個々に検討。それをグループ内で発表し合い、どんな質問が必要かを集約していく。家族状況、身体状況、経済状況など、まずどこに注目するかは人によって違う。自分と他者の視点の違いに気づくことによって、自分に足りない視点を知ることができるというわけだ。
その後は各グループからの質問に事例提供者が応答。ここでのポイントは、一問一答で質疑応答を行うこと。限られた時間での事例検討では、質問を絞り込み、優先順位が高い情報を的確に得ていくことが大切だ。答える側も、検討課題解決に向け、コンパクトに答えて焦点がぼけるのを防ぐ姿勢が求められる。

各グループとの質疑応答のあと、さらに不足している情報をSVor役の白木氏が尋ねていく。各グループからの質問が現時点での困りごと、家族状況、身体状況など、現在情報に集中していたことから、本人の生活歴など、どういう時代に、どんなことを大切にしながら生きてきたのか、という質問が中心となった。「現在情報だけでなく、過去も含めた本人を中心とした情報がないと、支援のための見立てはできない」と白木氏。
また、グループから出された「本人と子どもの関係はどうですか」という質問に対して、「事例提供者が主観で答えることになる質問ではなく、たとえば『母の日には子から連絡があるか』等、客観的事実を尋ねて、そこから関係性を把握することが大切」との指摘もあった。
このあと、各グループで事例を深める質問を再度検討し、発表するという作業が行われた。最後の講評で白木氏は、「みなさんは、目先の困りごとへの手だてを考え、どのサービスで対応するかを思い浮かべながら質問を発してはいないか」とズバリ。対象者に近づこうという姿勢があっても、支援に必要な情報を的確に得る質問力を身につけないと、近づくことはできないと訴えた。
研修の最後に参加者からは、「中身が濃い。来てよかった」「多様な見方があると感じ、グループワークの大切さを痛感した」「全国にこれだけ意欲的なケアマネジャーがいると感じられ、パワーをもらった」など、生き生きとした感想が口々に語られた。
次回研修は9月15日(土)。的確に事例をまとめる方法と技術の習得を目標に開催される予定だ。
(ケアマネジメントオンライン 2012/05/23 12:00 配信)
5月12日に開催されたケアマネジメントキャリアアップ研修「ケアマネジメントとは何か」。ここでは研修の後半に行われた、5、6人ずつでのグループワークの様子を紹介する。
この研修の到達目標は、ケアマネジメント実践上の課題を明らかにすること。的確なアセスメント力を身につけるには、事例検討会で事例を深め、展開していく力を養うことが役に立つ。グループワークは、事例を深める上で自分に足りないアセスメントの視点、分析力に、他者との対比の中で気づくことを目的に行われた。
まず事例提供者から、模擬事例のプレゼンが行われた。時間は10分。「事例検討では検討課題を明確化し、10分で要点をまとめてプレゼンする力が求められる」と白木氏。聞く側は頭の中で情報を整理し、何を質問すればこの事例がわかるかを考えながら聞くことが大切。そして、スーパーバイザー(以下、SVor)は情報を板書し、図式化していくことで、同席者が情報を共有しやすくする。出席者全員で板書の情報を共有すること、つまり配布された事例の資料に個々で情報を書き込むのではなく、全員が顔を上げて事例提供者のプレゼンを聞けるようにすることも重要だという。
研修では、このあと事例を深める質問を個々に検討。それをグループ内で発表し合い、どんな質問が必要かを集約していく。家族状況、身体状況、経済状況など、まずどこに注目するかは人によって違う。自分と他者の視点の違いに気づくことによって、自分に足りない視点を知ることができるというわけだ。
その後は各グループからの質問に事例提供者が応答。ここでのポイントは、一問一答で質疑応答を行うこと。限られた時間での事例検討では、質問を絞り込み、優先順位が高い情報を的確に得ていくことが大切だ。答える側も、検討課題解決に向け、コンパクトに答えて焦点がぼけるのを防ぐ姿勢が求められる。

各グループとの質疑応答のあと、さらに不足している情報をSVor役の白木氏が尋ねていく。各グループからの質問が現時点での困りごと、家族状況、身体状況など、現在情報に集中していたことから、本人の生活歴など、どういう時代に、どんなことを大切にしながら生きてきたのか、という質問が中心となった。「現在情報だけでなく、過去も含めた本人を中心とした情報がないと、支援のための見立てはできない」と白木氏。
また、グループから出された「本人と子どもの関係はどうですか」という質問に対して、「事例提供者が主観で答えることになる質問ではなく、たとえば『母の日には子から連絡があるか』等、客観的事実を尋ねて、そこから関係性を把握することが大切」との指摘もあった。
このあと、各グループで事例を深める質問を再度検討し、発表するという作業が行われた。最後の講評で白木氏は、「みなさんは、目先の困りごとへの手だてを考え、どのサービスで対応するかを思い浮かべながら質問を発してはいないか」とズバリ。対象者に近づこうという姿勢があっても、支援に必要な情報を的確に得る質問力を身につけないと、近づくことはできないと訴えた。
研修の最後に参加者からは、「中身が濃い。来てよかった」「多様な見方があると感じ、グループワークの大切さを痛感した」「全国にこれだけ意欲的なケアマネジャーがいると感じられ、パワーをもらった」など、生き生きとした感想が口々に語られた。
次回研修は9月15日(土)。的確に事例をまとめる方法と技術の習得を目標に開催される予定だ。